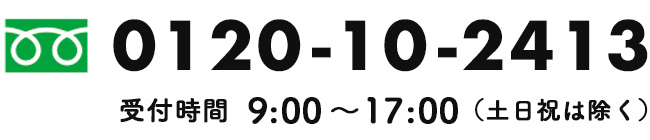サービス提供責任者は、訪問介護事業所に1名以上の配置が義務付けられています。ご利用者のサービスやヘルパーの働き方など、事業所全体をコーディネートする重要な役割な役割を担う、訪問介護にはなくてはならない存在です。
やりがいのある仕事ではありますが大きな重積を担うため、大変に感じて「辞めたい」と悩む方もいるのではないでしょうか。
今回の記事ではサービス提供責任者が辞めたいと思う理由を解説します。その対処法や続けることのメリットも解説しますのでお悩みの方は参考にしてください。
サービス提供責任者を辞めたいと思う理由

サ責の仕事はご利用者のサービス全般に関わることに加え、ヘルパーのスケジュール管理やマネジメント・ご家族対応・請求業務など多岐にわたります。兼務も認められているため、ヘルパーとして介護業務に入ることも多いでしょう。
多忙な中、これらの業務をスケジュール調整してこなしていかなければならず、負担に感じてしまう方も多いかも知れません。辞めたいと思う具体的な理由を見ていきます。
プライベートの時間が取れない
サ責の仕事は非常に幅広く、多くのことを求められるため日々の業務は多忙を極めます。結果、なかなか十分なプライベートな時間が確保できないことが辞めたいと思う原因になる方もいるようです。
ご利用者は自宅で生活されているので、24時間365日の対応が必要です。施設介護であればそのときに勤務しているスタッフが対応してくれますが、在宅介護ではそうはいきません。早朝・夜間・土日祝・お盆や年末年始も関係なくご利用者の生活は続いています。何かあれば急遽対応が迫られることも少なくありません。
ヘルパーのスケジュール管理も大変です。何らかの理由でサービスに入れなくなった場合はスケジュール調整を行い、場合によっては代わりにサービスに入ることもあります。退勤後や休日にも、困ったことがあればヘルパーから連絡が入ることもしばしばです。
プライベートの時間が取れない状態が続き、精神的に負担を感じる人が多いようです。
体力的にキツい
訪問介護は施設介護と違い、サービスを行う環境がまちまちです。場合によっては困難な環境の中で対応しなければなりません。設備などが整っていない中での介護は体力的に負担に感じてしまう場合もあります。ご自宅への移動があるのも大変です。暑い日も寒い日も、天候が悪い日でもサービスごとに移動しなければならないため、体力的に疲弊するという声も多くあります。
頼れる理解者・相談相手がいない
訪問介護事業所のサービス提供責任者の配置人数は法令によって定められています。大規模な事業所であれば複数名配置されていますが、一人だけの事業所も少なくありません。スタッフからの愚痴や利用者からのクレームなどの対応に追われる一方、同じ目線で話ができる人が職場にいなければ、精神的にキツいと感じてしまうでしょう。
また、十分な引き継ぎがないままに就任してしまうケースもあり、負担感を感じたり、辞めたいと思ってしまう方もいるかもしれません。
人間関係にストレスを感じる
サ責は訪問介護に関連する多くの人と連携しながら行う仕事なので、人間関係がストレスになる場合も多いですよね。
ご利用者はもちろん、そのご家族に対しても困難な事例には的確に判断して対応していかなければなりません。時には理不尽なクレームやトラブルもあります。ケアマネジャー・看護師・他事業所職員・主治医などさまざまな立場の方とも連携を取らなければならないため、対応に難しさを感じることもあるかもしれません。
また、ヘルパーのマネジメントが難しい場合もあるでしょう。ヘルパー同士の人間関係の仲介をしたり、時にはベテランヘルパーに対して指導したりする場面も出てきます。
それぞれの立場で物事を考えなくてはならないため、板挟みになりそれがストレスになるケースがあります。
業務負担の割に報酬が見合わない
サ責の月収は処遇改善手当によりだいぶ改善されつつあるものの、まだほかの業界に比べると低いのが現状です。これまで説明してきたようなサ責の業務負担を考えれば、報酬が見合わないと感じる方も多いでしょう。
ほかの介護職の方に比べると高く設定されていますが、報酬により評価されなければ辞めたくなる原因になります。
サービス提供責任者を続けるメリット

大変な職種ではありますが、一方でサービス提供責任者を辞めずに続けるメリットにはどのようなものがあるでしょうか。
やりがいが感じられる
サ責には、在宅で生活を続けたい方を支援する役割があります。最期までご自宅で過ごしたい方の希望を叶え、その方らしい生活を実現させる仕事には大きなやりがいが感じられるでしょう。在宅介護ではご利用者一人ひとりに合わせたサービスが提供できるため、ご利用者やその家族から感謝してもらえることも多く喜びが感じられます。
人材不足が深刻な中ますます需要が高まっている介護業界で働くことは、社会貢献につながるといった点でも意味のあるお仕事です。
スキルが身に付きキャリアアップにつながる
サ責を経験しておくと、さらなるキャリアアップのチャンスが広がります。
ご利用者やご家族との関わりだけでなく、ケアマネや看護師などの他職種との関わりを通して多くの知識が身に付き、ヘルパーとの関わりからはマネジメント力も培われます。多くの方と関わりながら仕事をするので、コミュニケーション力もアップし人間としての成長も期待できるでしょう。
また、サ責の仕事は将来的にケアマネジャーを目指す方にも非常に役立ちます。介護保険制度や行政対応、介護報酬請求など事務的な業務も多いため自然と知識が身につきます。実際にケアマネジャーと関わりながら仕事をするので、どのような仕事をしているのかを身近で学ぶことができるでしょう。
安定した働き方ができる
介護職は低賃金と言われますが、サ責は介護職の中では給料が高く設定されています。「令和4年度介護労働実態調査」によると、サービス提供責任者の通常月の税込み月収は243,312円でした。訪問介護員が188,435円なので、サ責になれば5,5000円程度月収がアップすることが分かります。
正社員として採用されることが多いため、安定した働き方ができるのもサ責をするメリットです。
参考:公益財団法人 介護労働安定センター「令和4年度介護労働実態調査」
サービス提供責任者を辞めたいと感じた時の対処法

どうしても辞めたいと感じたら、以下の対処法を試してみてください。
相談相手をつくる
サ責の仕事は大きな責任を伴うため、さまざまな不安や悩みが出てきます。そんな時にすぐに相談できる相手を作っておくことが大切です。
事業所内で同じ立場の人がいない場合は、他の職種などでも良いので身近に悩みを打ち明けられる相手を作っておくとそれだけでも気持ちが楽になります。
身近に話ができる人がいない場合、研修などに参加して他の事業所のサ責と交流を深めたりするのもおすすめです。情報交換する関係性が構築できれば分からないときや迷ったときに相談でき、安心して業務が進められます。最近は、X(旧Twitter)などSNSでつながっている人もたくさんいます。非対面なので気持ちを吐き出しやすく、ストレス解消の一助になるようです。
職場環境を見直す
少しでも働きやすい職場にするためには、一人で抱え込まず管理者やヘルパーなどに相談し、環境を見直す努力をすることも大切です。ご利用者のケアに関することや勤務体制のことなど些細なことでも改善に向けてこまめに相談するようにすると周囲とのコミュニケーションも良好になります。
サービス提供責任者は、立場上、人間関係をコントロールしたり、業務効率を改善するなど、ある程度の裁量権もありますよね。自分がこの職場を変えてみせる!と、前向きに捉えて努力してみるのもひとつではないでしょうか。
ちなみに、業務効率をあげるアイテムには以下のようなものがあります。
- チャットツール(連絡・情報共有)
- オンライン会議ツール
- 介護ソフト(情報共有・介護記録・請求業務・労務管理)
- 見守りシステム
- 排泄予測システム
- 給与計算システム
こうしたツールを使って少しでも業務の手間を減らし、快適に働けるように工夫しましょう。
自分に合う職場に転職する
サ責は続けたいけれど、どうしても職場環境が合わないという場合は、違う事業所で条件の良い職場に転職するのも一つです。同じ仕事でも働く人や環境が違えば、働きやすくなるかもしれません。
どうしてもサ責特有の働き方が合わない方は、ほかにも介護職の働き方はたくさんあります。現場が好きな方は訪問介護事業所のヘルパーとして働くのも良いですし、施設介護や通所介護など違う働き方に挑戦するのも良いでしょう。
いずれにしてもサ責としてのキャリアが評価されるため、自分に合うより良い職場が見つけやすいはずです。
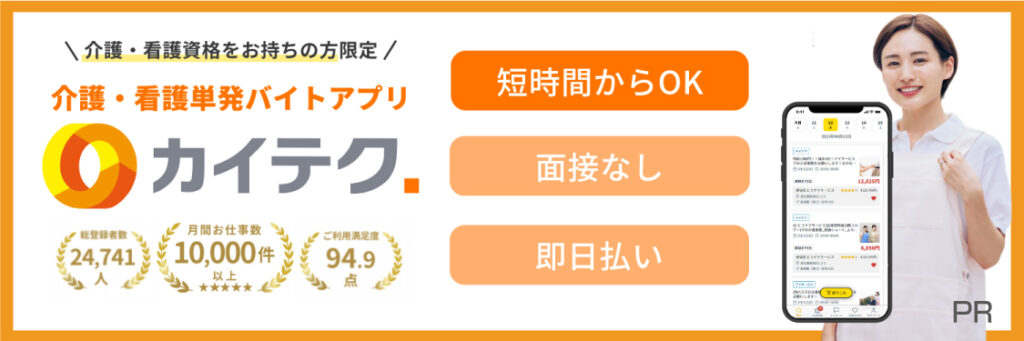
働きやすい環境づくりを工夫しよう
訪問介護のサービス提供責任者は、介護職の中でも業務の範囲が多岐にわたり幅広い知識が求められる仕事です。辞めたいと感じてしまうくらい大変に感じる方も多いかも知れません。
しかし、やりがいがあり将来のキャリアアップにつながる仕事であることは間違いありません。無理なく仕事が継続できるように働きやすい環境作りを工夫しましょう。

サ責の業務負担を軽減する介護ソフトでおすすめなのが、訪問介護のサービス実施記録をLINEで報告できる「テレッサモバイル」です。
テレッサモバイルを利用すれば、ヘルパーさんからLINEで業務の報告が送られてくるのでリアルタイムでサービス状況を確認することが可能になります。月末月初の忙しい時期にも、実施記録の提出を待つことなく介護報酬請求業務に取り掛かれます。
こうしたITツールを活用することで、場所を選ばず仕事ができることも魅力のひとつ。工夫次第で介護業界もより働きやすくなっていくでしょう。
ITツールを活用することで、加算取得などにもメリットがあります。
業務を効率化して少しでも負担が軽減できるようにぜひ検討してみてください。
投稿者プロフィール

-
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則
お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則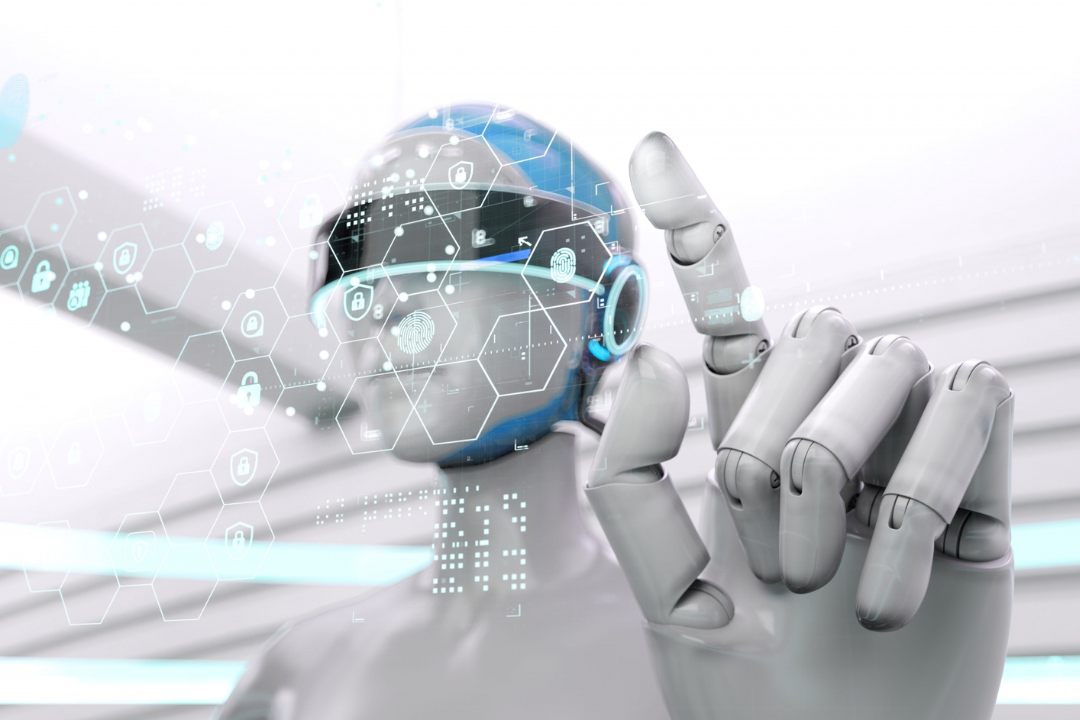 コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント
コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方
お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方 お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ
お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ