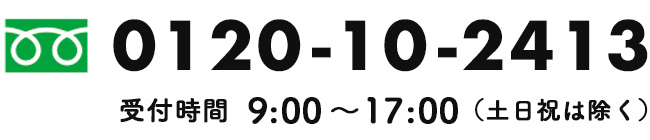介護報酬の不正請求は、事業所の存続をおびやかしかねない重大な問題です。近年、行政の取り締まりが強化される中、不正請求の事例が後を絶ちません。この記事では、介護事業所の運営者や管理者の方に向けて、不正請求の実態や予防策について解説します。適切な請求業務の実施とコンプライアンス体制の構築に役立ててください。
介護報酬不正請求の実態

まずは、不正請求の定義や概要、近年の傾向について解説します。
介護事業所の運営者や管理者が不正請求のリスクを理解し、適切な対策を講じる上で重要な情報を確認しておきましょう。
介護報酬不正請求の定義と概要
介護報酬の不正請求とは、介護サービス事業者が実際には提供していないサービスや、基準を満たしていないサービスに対して介護給付費を請求し、不当に受給する行為を指します。例えば、虚偽書類の作成・サービス提供時間の水増し・資格要件を満たさない職員によるサービス提供などが該当します。
これらの行為は介護保険法や障害者総合支援法に違反するため、厳しい処分の対象です。制度の複雑さが原因で、知識不足により結果的に不正請求になってしまうケースもあります。しかし、単なる事務ミスではなく、意図的な虚偽報告や記録の改ざんは、悪質な行為として扱われるため注意が必要です。
近年の不正請求の傾向
最近の不正請求の傾向は、複雑化・巧妙化しています。
例えば、モニタリングの記録不備や居宅サービス計画の不適切な作成など、書類上の不備を隠蔽するケースです。また、タイムカードや出勤簿、業務日誌などの虚偽作成などの事例も少なくありません。
特に注目すべきは、個別機能訓練加算など、各種加算の不正請求が増加傾向にあることです。これらの不正は、単発ではなく長期間にわたることが多いため、発覚時には多額の返還金が発生するリスクがあります。
不正請求の発覚経緯と行政の対応

介護事業所の運営者は、不正請求の発覚から行政処分に至るまでのプロセスも理解しておく必要があります。不正請求がどのように明らかになり、行政がどのように対応するかについて理解しておきましょう。
不正請求の発覚経緯
不正請求の発覚経路は多岐にわたります。主な経路は以下のとおりです。
- 内部告発
- 利用者や家族からの通報
- 他の事業者からの情報提供
- 行政による監査や運営指導
内部告発の場合、従業員が良心的な判断から通報するケースがあります。他にも、利用者や家族からの疑問や苦情が調査のきっかけとなることもあるため、サービスの透明性確保が不可欠です。
運営指導と監査
行政による調査は「運営指導」と「監査」の2段階で行われます。
運営指導は定期的に実施され、介護サービスの質の確保と向上を目的としています。一方、監査は不正請求の疑いがある場合に実施される厳格な調査です。
運営指導はかつて「実地指導」と言われていましたが、実地だけでなくオンラインでの確認を行うようになったため、名称が「運営指導」へ変更になっています。運営指導で確認する内容は、介護サービスの実施状況や最低基準等の運営体制などです。実施頻度は、原則として事業所の指定有効期間である6年に1回は実施されることになっています。
一方監査は、人員基準違反や運営基準違反、不正請求の疑いがある場合に行われ、担当者への質問や現地での検査が実施されます。監査は事前通告なしで行われることがあり、違反や不正の内容に応じて指導や行政処分が決定されます。
行政処分の種類
行政処分の種類は、不正の程度や内容によって異なります。軽微な場合は口頭指導や文書指導から始まり、重大な違反の場合は指定の一部効力停止、全部効力停止、そして最も厳しい処分として指定取消が行われます。
指定取消処分を受けると、事業所の存続が困難になるだけでなく、職員の雇用にも大きな影響を与えるため、コンプライアンスの徹底が不可欠です。
不正請求を防ぐための対策と体制づくり

不正請求を防ぐためには、組織全体でのコンプライアンス体制の構築が欠かせません。ここからは、コンプライアンス体制の強化について解説します。
組織全体のコンプライアンス体制を強化
コンプライアンス体制を構築するためには、まず経営者自身が法令遵守の重要性を理解し、組織全体に浸透させることが重要です。具体的な施策としては、コンプライアンス委員会の設置、内部通報制度の整備、定期的な内部監査の実施などが挙げられます。
また、業務プロセスの定期的な見直しも効果的です。介護保険法の改正に合わせて、自社の規程やマニュアルを更新する体制を整えることが重要です。弁護士、会計士など、外部の専門家との連携を強化し、客観的な視点からのチェックを受けることも有効です。
職員の教育とモラル向上
職員教育とモラル向上は、不正請求防止の要となります。
まず、全職員を対象とした定期的なコンプライアンス研修を実施するようにしましょう。研修では、介護保険制度の基本的な仕組み、請求業務の重要性、不正請求の事例と影響などを学びます。これらの研修は、入社時研修や事業所の年間研修スケジュールに組み込み、計画的に実施することが大切です。
また、職員のモラル向上には、組織の理念や価値観の共有が不可欠です。経営者や管理者が率先して倫理的な行動を示し、組織の使命や社会的責任を共有することが重要です。職員の声に耳を傾け、業務改善や職場環境の向上に取り組むことで、職員の帰属意識と仕事への誇りを高めることが期待できます。
具体的な取り組みとしては、グループディスカッション、外部講師を招いてのセミナーの実施などが挙げられます。他にも、資格取得支援や専門性向上のための研修参加を奨励することで、職員の成長意欲を促し、同時にサービスの質の向上にもつなげることができます。
自主点検による請求業務の適正化
請求業務の適正化には、定期的な自主点検が不可欠です。自主点検では、サービス提供記録と請求内容の照合、加算要件の確認、利用者負担金の計算チェックなどを行います。特に注意すべきポイントとして、モニタリング記録の適切な作成、居宅サービス計画との整合性確認、タイムカードや業務日誌とのつき合わせなどが挙げられます。
さらに、複数の目で確認するダブルチェック体制の構築や、定期的な外部監査の実施も検討しましょう。これらの取り組みにより、不正請求のリスクを大幅に低減し、適正な請求業務を実現することができます。
自主点検の結果は必ず記録し、改善点を明確にしてPDCAサイクルを回すことが重要です。組織全体で課題を共有することで、継続的な改善につながります。
IT化による効率化
ITツールの活用も効果的です。例えば、請求ソフトウェアの導入により、人為的ミスを減らし、データの一元管理が可能になります。IT化により情報共有がしやすくなったり、記録時間が削減したり、職員の業務負担を軽減することにもつながります。
日本でも 国をあげてIT導入が推進されていますが、介護業界で働く方にはITツールに苦手意識を持つ方も多く、導入が遅れているところもあります。しかし、IT化を推進することは、ミスの削減だけでなく人材不足の解消にも効果的です。不正を防ぎ適正な記録を残すために、介護事業所においてもIT化は必須なものとなっています。
適切な介護報酬請求のために

介護報酬の不正請求は、事業所の存続を脅かすだけでなく、介護保険制度全体の信頼性を損なう重大な問題です。
適切な介護報酬請求を実現するためには、組織全体でのコンプライアンス意識の向上、請求業務の適正化と定期的な自主点検、職員教育とモラル向上の取り組みを行うこと、請求の人的ミスを減らすことが大切です。
これらの取り組みを通じて、不正請求のリスクを最小限に抑え、利用者と社会から信頼される介護サービス事業を展開することができます。適切な介護報酬請求は、単なる法令遵守にとどまらず、質の高いサービス提供と健全な経営の基盤となるものです。今後も、制度の変更や社会のニーズに柔軟に対応しながら、継続的な改善と向上に努めていきましょう。
テレッサモバイルで事務作業を効率化しよう

事務作業負担を軽減し、適正に介護請求を行うには「テレッサモバイル」がおすすめです。テレッサモバイルは訪問介護の記録に特化した、シンプルな介護記録管理アプリです。
幅広い世代で使用されているLINEで報告するので、年配ヘルパーさんにもすぐに慣れていただけると好評です。送られてきた介護記録は自動で実績のチェックも可能(ベーシック版)。業務が効率化でき、大幅な負担軽減につながります。
まずは記録からシステム化し、事務作業をラクにしませんか?
投稿者プロフィール

-
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則
お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則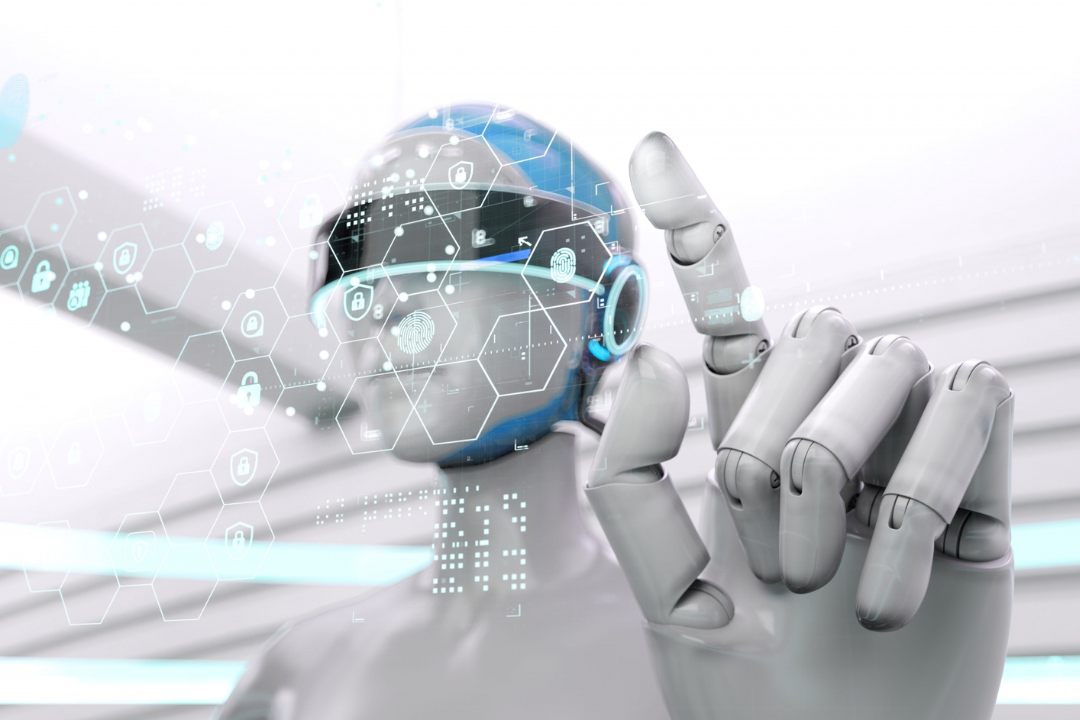 コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント
コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方
お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方 お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ
お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ