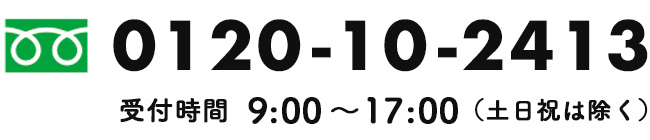介護事業所では多くの書類を法令に基づいて適切に保管する必要がありますが、保存期間や管理方法に悩んでいる管理者の方も多いのではないでしょうか。
書類の不適切な管理は法令違反や監査での指摘につながるリスクがあり、一方で保管スペースの確保や業務効率化も重要な課題です。
本記事では、介護書類の法的保存期間から保管方法、セキュリティ対策、効率的な廃棄方法まで、実務に即した具体的なノウハウを解説します。
適切な書類管理により、法令遵守と業務効率の両立を目指しましょう。
介護書類保管の法的義務と基本知識

介護事業所の書類管理は介護保険法により厳格に定められており、適切な保管を怠ると法令違反として行政処分の対象となる可能性があります。
対象となる書類は、サービス提供記録、介護計画書、契約書、苦情対応記録、事故報告書など多岐にわたります。これらの書類は単に保管するだけでなく、必要時に速やかに提示できる状態で管理しなくてはなりません。
書類を利用者別や種類別にファイリングして整理し、鍵付きキャビネットでの保管により個人情報の漏洩を防止することも重要です。最近では、クラウドを活用した電子化が主流になりつつあります。
いずれの場合も、取り扱いの責任者を明確にし、職員全体で保管ルールを共有することが求められます。
書類別保存期間の詳細
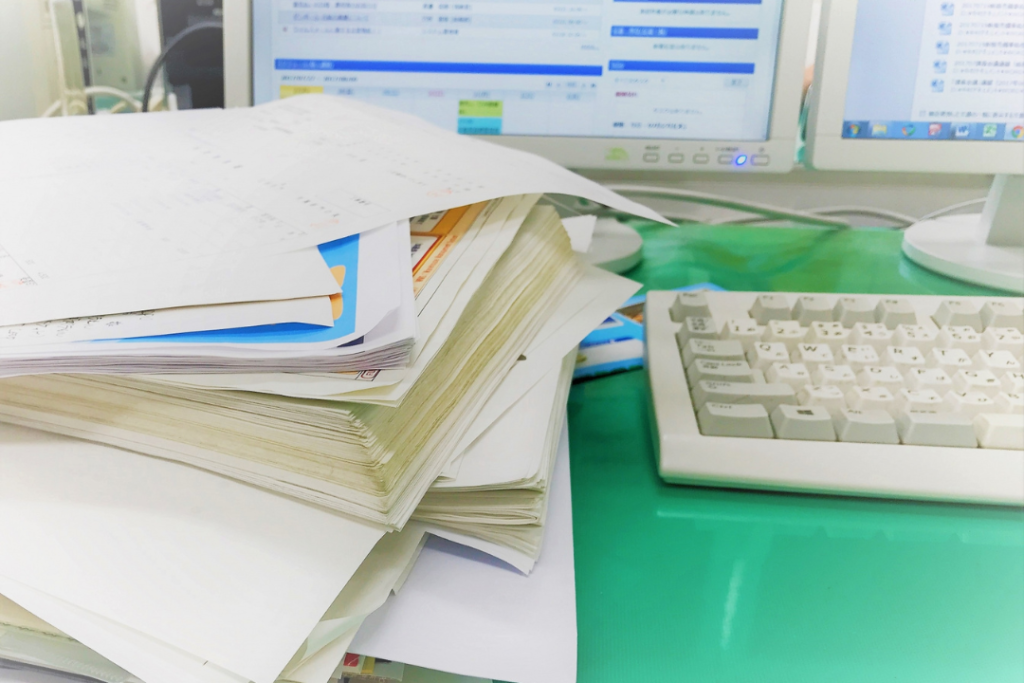
介護書類の保存期間を正しく理解することは、適切な書類管理の第一歩です。保存すべき期間を過ぎる前に誤って廃棄してしまうと法令違反となり、逆に必要以上に長期間保管し続けると保管スペースの圧迫や管理コストの増大につながります。
各書類の保存期間を把握して計画的な管理を行いましょう。
サービス提供記録の保存期間と「完結の日」の解釈
サービス提供記録の保管期間は、介護保険法施行規則により「サービス提供が完結した日から2年間」と定められています。この「完結の日」とは、利用者との契約が終了した日または最後のサービス提供日のことです。
具体的には、ご利用者が入院や施設入所により在宅サービスが終了した日、利用者が亡くなった日などが該当します。
保管対象となるのは、日々のサービス提供記録、介護計画書、クレームや事故の報告書などの利用者のサービス内容に関する記録です。これらの記録は利用者の安全と適切なケア提供の証拠となるため、詳細かつ正確な記載と確実な保管が求められます。
介護給付費請求書・明細書の5年間保存
介護給付費に関する書類は、5年間の保存が望ましいとされています。これは自治体の債権消滅時効が5年であることに対応した期間設定です。
対象書類には、国保連合会への請求書、介護給付費明細書、返戻や過誤申請に関する書類はもちろん、電子請求の際の国保連の請求データなども含まれます。請求システムのデータベースだけでなく、印刷物やバックアップメディアでの保存も検討し、システム障害時にも対応できる体制を整えておきましょう。
保管期間は法令と自治体によって異なる
国の基準では2年間とされているサービス提供記録も、自治体によっては条例により5年間の保存を求められる場合があります。この差異は、各自治体の指導監査方針や地域の実情を反映したものです。
保管期間は、自治体ホームページや運営指導の資料などで確認し、不明な点は介護保険課や指導監査担当部署に直接問い合わせることが確実です。複数の自治体でサービスを提供している場合は、最も厳しい基準に統一することでリスクを回避できるでしょう。
適切な書類廃棄方法とセキュリティ
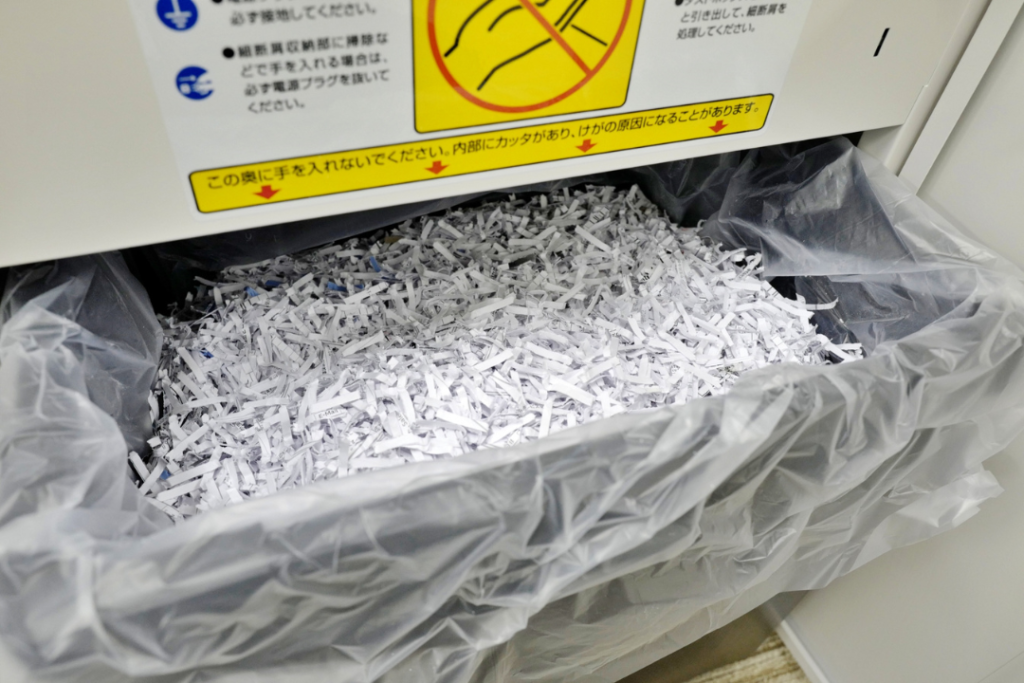
保存期間を経過した書類の廃棄は、個人情報保護に配慮した安全な方法で実施する必要があります。不適切な廃棄は情報漏洩リスクを生み、事業所の信頼失墜や損害賠償責任を招く恐れがあるため注意が必要です。
シュレッダー処理など基本的な廃棄の注意点
個人情報を含む介護関連書類の廃棄では、内容が判読不能になるまで完全に破壊することが重要です。単純にゴミ箱に捨てるだけでは情報漏洩のリスクが高く、利用者の個人情報が第三者に知られる可能性があります。
シュレッダー処理の場合は、復元困難なレベルまで細断します。家庭用の簡易シュレッダーではセキュリティが不十分な場合があるため、業務用のクロスカットシュレッダーの使用が推奨されます。また、処理後の紙片は複数回に分けて廃棄するとより確実です。
専門業者による溶解処理サービスの活用
溶解処理サービスは、書類を完全に溶かして復元不可能にする処理方法です。シュレッダー処理と比較して安全性が高く、大量処理にも対応できるため、多くの介護事業所で活用されています。
大量の書類廃棄では、専門業者への委託が効率的で、委託先選定ではプライバシーマーク取得状況、機密保持契約の内容、処理施設のセキュリティ体制を確認し、信頼できる業者を選択しましょう。
サービス利用時は、専用の密閉容器に書類を投入し、業者が回収後に溶解処理を行います。処理完了後には処理証明書が発行され、適切な廃棄の証拠として保管できます。
書類廃棄時は、廃棄日時、対象書類の種類と数量、廃棄方法、立会者名を記載した廃棄記録を作成し、この記録は適切な廃棄の証拠となるため、廃棄した書類の保存期間以上に保管することが望ましいです。
電子保管・デジタル化の導入と運用

書類の電子化は保管スペース削減と業務効率化に大きく貢献しますが、法的要件を満たす適切な運用が必要です。電子保存の要件と安全なシステム選択により、ペーパーレス化のメリットを最大限に活用しましょう。
介護書類の電子保存で注意すべき点
令和3年度介護報酬改定により、利用者への説明・同意について電磁的な対応が原則認められ、介護記録の電子保存も明確に容認されました。ただし、電子保存では記録の信頼性確保、必要時の閲覧性、長期保存性の確保が欠かせません。
「記録の信頼性確保」では、作成者の識別、作成日時の記録、改ざん防止措置が重要です。電子署名やタイムスタンプ機能を活用し、記録の信頼性を担保します。
「必要時の閲覧性」については、速やかに画面表示・印刷できる状態が求められます。
「長期保存性の確保」では、保管期間中のデータ消失防止とバックアップが必要です。クラウドストレージの活用により、災害時でもデータ保護を実現できます。定期的なデータチェックにより、長期保存時のデータ劣化も防止しましょう。
安全なクラウド保管システムの選択
クラウド型の電子保管システムは、近年多くの介護事業所で導入が進んでいます。物理的な保管スペースが不要であり、災害時でもデータが守られるという大きな利点があります。
システム選定にあたっては、次の点を重視しましょう。
- サーバーが国内にあり、個人情報保護法に準拠しているか
- アクセス権限管理やIP制限など、高度なセキュリティ機能があるか
- 自動バックアップと復元機能があるか
万が一の障害時に備えて、サポート体制やデータのエクスポート機能の有無も確認しておきましょう。特に、ペーパレス化が進むほど一元管理に依存するため、障害時の対応策を事前に明確にしておくことが重要です。
介護記録ソフト導入による業務効率化
介護記録ソフトを活用することで、現場の記録作業や事務処理が大幅に効率化されます。記録のテンプレート化や入力の自動補完機能により、職員の記録ミスや入力漏れが減少し、事務作業の負担も軽減されます。タブレットやスマートフォンでの入力により、現場での即座な記録作成も可能です。
また、記録がデジタル化されることで、検索や共有が簡単になり、多職種間の情報連携もスムーズになるのもメリットです。情報収集効率も向上し、より質の高いサービス提供が可能になります。
紙の記録をそのまま電子データに
既に紙で記録した介護記録は保管場所を取り、検索性も悪いものです。
紙の記録をスキャニングし、データに変換してくれるサービスもあります。一度は自事業所で実施したという方も多いのではないでしょうか。実際にやってみると、時間と手間ばかりかかってしまい、結局諦めたというケースは多いですよね。
こうした作業を委託できるサービスがありますので、検討してみてはいかがでしょうか。
トラブル防止と監査対応のポイント

書類管理のトラブル防止には、組織的に管理体制を構築し、継続的な改善を行うことが必要です。実地指導への準備、情報漏洩防止、災害対策、職員教育を総合的に実施し、安全で確実な書類管理を実現しましょう。
実地指導・監査への万全な準備
実地指導や監査では、書類の保管状況、記録内容の適切性、保存期間の遵守といった点が重点的に確認されます。提出を求められる書類は、介護記録、計画書、契約書、請求書類など多岐にわたります。
これらに円滑に対応するためには、保存期間に応じたファイリングを整備し、いつでも提出できる状態を維持しておくことが重要です。また、チェックリストを活用し、必要書類の所在確認と内容の精査を定期的に実施することで、書類管理の精度を高めることができます。
さらに、書類の電子化を進めることで、検索性や保管性が向上し、実地指導や監査にもスムーズに対応できます。
情報漏洩防止のためのリスク管理
紙・電子を問わず、書類管理には常に情報漏洩のリスクが伴います。利用者の個人情報や医療情報が外部に流出した場合は深刻な信用問題に発展するおそれがあるので、特に注意が必要です。
漏洩対策として、紙の資料は鍵付きキャビネットに保管し、閲覧可能な職員を限定することが基本です。電子データには、パスワード管理や二段階認証、アクセス権限の細分化など、段階的なセキュリティ対策が求められます。
また、職員が無意識に使用してしまうUSBメモリや私物PCは、重大な情報事故につながる可能性があります。これらの使用を禁止する明確なルールを定め、全職員に対して徹底した教育を実施することが重要です。
災害時の書類保護とリスク管理
自然災害や火災などの緊急時に備え、重要書類の保護対策を講じる必要があります。耐火金庫での保管、バックアップ保存、クラウドストレージの活用により、災害時の書類消失リスクを軽減することが可能です。
事業継続計画(BCP)に書類管理の継続手順を盛り込み、災害時でも最低限の業務継続を可能にします。電子化により、避難先からでも必要な情報にアクセスできる体制を構築しましょう。
また、定期的な災害対応訓練により、職員の対応力向上と手順の実効性確認を行うことが大切です。災害時の対応マニュアルや、書類の優先保存リストを作成しておくと、緊急時の混乱を最小限に抑えることができます。
職員教育と管理体制の構築
書類管理を徹底するには、全職員の理解と協力が不可欠です。どれほど優れたシステムやルールが整備されていても、実際の運用が徹底されていなければ意味がありません。
そのため、新人研修や定期研修を通じて、法的要件や事業所独自の管理方針をしっかりと周知させることが重要です。加えて、具体的な作業手順をマニュアル化し、誰もが同じ対応を取れる体制を整えておく必要があります。
さらに、情報管理に関する誓約書の取り交わしや教育記録の保管を行うことで、トラブル発生時のリスクに備えることができます。
効率的で安全な介護書類管理の実現を

介護記録の適切な保管と処分は、法的義務であると同時に、利用者の権利保護や事業所の信頼維持に直結する重要な業務です。保存期間を把握したうえで、紙書類は鍵付きで保管し、期限後はシュレッダー処理や専門業者による廃棄など、漏洩リスクのない方法で確実に処分しましょう。
書類管理を電子化すれば、保管スペースの削減や検索効率の向上、職員の業務負担軽減にもつながります。今後の制度改正に対応するためにも、定期的な見直しが不可欠です。
介護記録を電子化するならテレッサモバイル

訪問介護で記録の電子化を検討する際には、LINEを活用して記録入力が行える「テレッサモバイル」も有力な選択肢です。
テレッサモバイルはバックアップ機能もあり、日々の介護記録をスムーズに保管することができます。記録の入力はヘルパーさんのスマートフォンで行い、リアルタイムで報告が可能。記録はクラウド上に保管されるため、保管場所が不要となり、検索性も向上します。
現場職員の負担を軽減しつつ、安全かつ効率的な記録管理をサポートします。最大2ヶ月無料で利用できるので、電子化を検討の方はぜひお試しください。
投稿者プロフィール

-
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則
お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則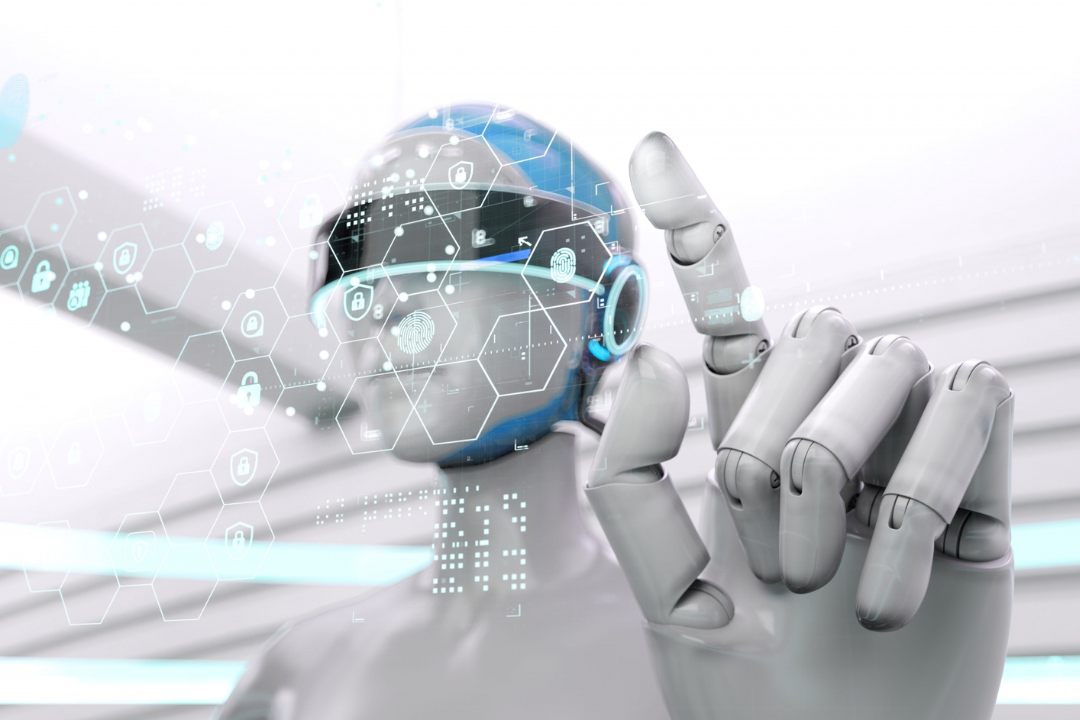 コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント
コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方
お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方 お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ
お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ