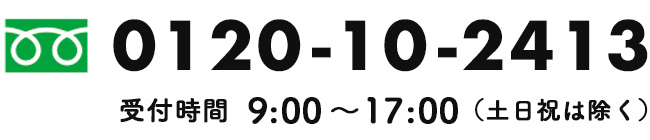訪問介護事業所では、すでに多くの現場で記録業務の電子化が進んでおり、今や電子化は特別な取り組みではなく、標準的な運用形態となりつつあります。ただし、その一方で「費用が心配」「スタッフの反発がある」といった課題を抱える事業所も少なくありません。
この記事では、そうした不安を整理し、どのように解決していくかを具体的に紹介します。ICT導入支援制度や補助金の活用法、職員研修やセキュリティ対策など、導入後に安定した運用を実現するためのポイントを解説しますのでぜひ参考にしてください。
導入前に知っておくべき現場の課題

介護記録の電子化を検討する際、多くの事業所で現場からさまざまな懸念の声が上がります。実際の導入事例から見えてきた、現場が抱える代表的な課題を整理してみましょう。
「ITは苦手」という職員の本音
実際の現場では「今まで紙で十分やってきたのに、なぜ変える必要があるのか」「タブレットなんて触ったこともない」といった声が聞かれます。特に経験豊富なベテラン職員ほど、新しいツールへの抵抗感が強いかもしれません。
現場でよく聞かれる声としては、次のような不安があります。
- 「慣れるまで記録に時間がかかって、利用者を待たせてしまうのでは?」
- 「操作方法を忘れて、利用者宅で困ったらどうしよう」
- 「急いでいる時に機械が動かなくなったら…」
こうした現場の不安や戸惑いは、システムの機能そのものよりも、電子化がうまく根付くかどうかに大きな影響を与えます。
経営陣が抱える投資への不安
管理者や経営者の立場では、「本当に投資に見合う効果があるのか」という根本的な疑問があります。タブレット端末一台あたり数万円程度の費用、記録ソフトの月額利用料、通信費、研修費用など、トータルで数十万円から数百万円の投資が必要になります。
「うちのような小さな事業所に電子化は必要ない」「職員が慣れるまでにかかる時間とコストを考えると、紙のままの方が良いのでは」という判断に至るケースも珍しくありません。
個人情報管理への不安
介護現場で最も神経を使うのが個人情報の取り扱いです。「タブレットを紛失したらどうなるの?」「落として壊したらデータは消えてしまうのでは?」「間違って他の利用者の情報を送信してしまったらどうしよう」といった具体的な心配から、「デジタルは何となく不安」という漠然とした懸念まで、セキュリティに対する不安は根強く残っています。
課題を乗り越える実践的解決策

現場の課題を踏まえ、多くの事業所で実践されている工夫や成功のポイントを参考に、具体的な解決策を紹介します。
段階的導入と個別サポートで操作不安を解消
最初からすべてを電子化するのではなく、まずは訪問介護職員が日常的に記入している「サービス実施記録」など、比較的扱いやすく定型化された記録業務から始めるとよいでしょう。職種や業務内容に応じて、「訪問介護計画書の作成」や「請求業務」など、事務的な記録領域へと範囲を広げていきます。
研修についても、集合研修だけでなく個別指導の時間を設け、事業所として継続的なサポート体制を整えると効果的です。
補助金活用と費用対効果の明確化
厚生労働省の「ICT導入支援事業」や自治体独自の補助金を活用すれば、導入費用の多くを補助でまかなえる場合があります。申請書類の準備は多少手間がかかりますが、費用削減効果を考えると十分検討する価値があります。
また、記録時間の短縮や紙代・印刷代の削減、保管スペースの有効活用など、導入後にどのような効果が得られるかをあらかじめ見積もっておくことで、投資に対する見通しが立てやすくなります。
徹底したセキュリティ対策と職員教育
セキュリティ対策としては、技術的な仕組みの整備だけでなく、職員一人ひとりの情報リテラシーを高める取り組みが欠かせません。
たとえば、情報セキュリティに関する研修を定期的に実施し、「なぜセキュリティが必要か」「どのような行動がリスクにつながるのか」といった基本を理解する機会を設けます。加えて、個人情報の取扱いや記録方法について、業務ルールの確認や注意点の共有を行い、全職員の意識を高めることが重要です。
このようなルール運用の徹底は、どのICTツールを導入する場合でも基盤となる部分です。
現場見学と参考施設の活用
ICTの導入を円滑に進めるためには、すでに電子記録を取り入れている事業所の運用を参考にすることが有効です。現場を実際に見学することで、画面操作や記録の流れを具体的に把握でき、導入前の不安軽減や職員の意識向上にもつながります。
また、自事業所と似た規模や運営形態の施設と情報交換を行うことにより、自分たちに合った運用方法を見つけやすくなります。すでにICT導入を進めている事業所があれば、見学を依頼して現場の工夫や運用の様子を学ぶのもよい方法です。
電子化を定着させるための継続的な取り組み

ICT導入は一度設定すれば終わりではありません。導入直後の効果を検証し、運用を定着させ、さらに長期的に活用していくための継続的な取り組みが重要です。
導入直後の効果検証と改善
ICT導入後は、まず期待していた効果が実際に現れているかを検証しましょう。記録時間の短縮、残業時間の減少、業務の見える化による情報共有の改善など、具体的な数値で効果を測定することが大切です。
また、職員のワークライフバランスの改善や定着率の向上といった間接的な効果についても、定期的なアンケートや面談を通じて把握しましょう。特に若手職員や子育て世代からの声を積極的に収集し、柔軟な働き方の実現に向けた改善点を見つけることが重要です。
運用定着のための継続的改善
電子化後も現場の業務状況は日々変化するため、定期的にフォローアップの機会を設け、職員の声を集めることが重要です。「使いにくい」「操作が煩雑」といった声があれば、その都度マニュアルを見直したり、サポート体制を強化したりして、運用の質を安定させましょう。
また、月1回など定期的な改善会議を実施し、ICTの活用状況やトラブル事例を共有することで、現場全体のICTリテラシーの向上を図ることができます。これにより、職員の納得感が高まり、定着率の向上にもつながります。
現場内に限らず、地域の事業所間で情報を交換することも積極的に行いましょう。電子記録の導入における成功事例や失敗事例を共有することで、他の事業所の経験から学ぶことができます。
中長期的な活用体制の整備
将来的な制度変化に対応できる体制づくりを進めましょう。LIFE(科学的介護情報システム)への対応や加算取得の可能性を見据え、導入するシステムの拡張性や将来性を検討することが大切です。必要に応じて、データの管理方法や出力形式を整備しておくことで、制度変更にも柔軟に対応できます。
また、報酬改定によってICT活用が評価される傾向を踏まえ、制度の変化にアンテナを張り、導入したICTの活用幅を広げる取り組みを継続しましょう。定期的にシステムの機能アップデートを確認し、新しい機能の活用方法を検討することで、業務の質向上と将来的な制度変化への対応力を高めることができます。
電子化を成功に導く最終チェックポイント

介護記録の電子化は、単なる業務のIT化にとどまらず、現場の働き方や利用者へのサービスの質を大きく左右する重要な取り組みです。今後の加算取得や科学的介護への対応を見据える上でも、電子化による記録整備は大きな強みになります。
成功の鍵は、職員のスキルアップと業務プロセスの継続的な改善です。定期的な研修の実施、現場の声を反映した運用改善、そして他事業所との情報共有を通じて、長期的な効果を実現できます。課題をひとつずつ解決しながら現場全体で取り組むことで、介護記録の電子化は事業所の持続的な発展と利用者により良いサービス提供のための重要な投資となるでしょう。
介護記録の電子化ならテレッサモバイルがおすすめ

介護記録の電子化をお考えの事業所には、LINEを活用した「テレッサモバイル」がおすすめです。普段から使い慣れたLINEをベースとしているため、職員の皆様にとって操作が分かりやすく、導入時の負担を大幅に軽減できます。ICT導入が初めての事業所でも安心してスタートできるシステムです。
また、テレッサモバイルはIT導入補助金の対象ツールとなっており、採択されれば初期導入費用の1/2~2/3の補助を受けることができます。できるだけ費用を抑えたいという事業所様はチャレンジしてみるといいでしょう。
介護記録を電子化することで特定事業所加算取得にも役立ちます。ぜひ前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール

-
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則
お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則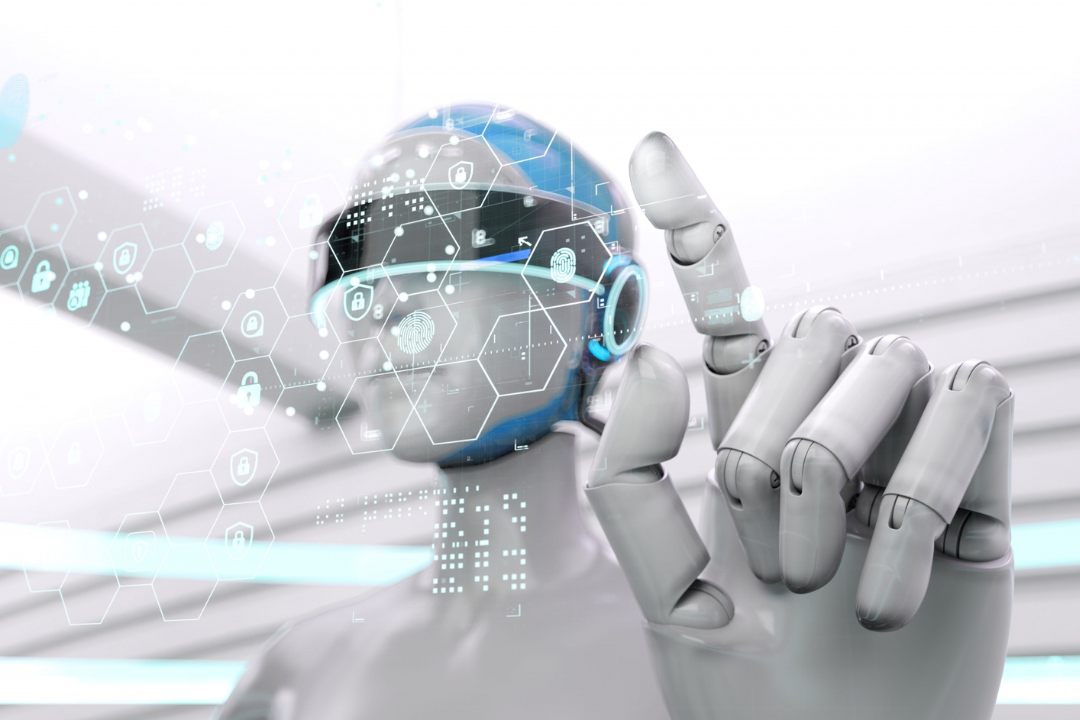 コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント
コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方
お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方 お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ
お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ