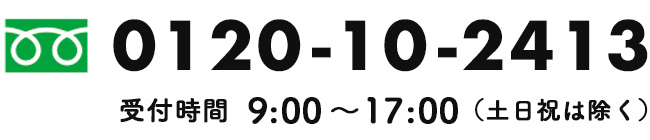訪問介護事業所で働く方の中には、看取り介護に不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。人生の最期にかかわる支援なので、不安になるのは当然です。
この記事では、看取り介護の際にご本人やご家族に必要な説明や、ヘルパーが気をつけなければならないことについて解説します。
ご自宅で最期を迎えたい方に寄り添うことは非常に尊い支援です。この記事を参考に看取り介護に向き合ってみてください。
看取り介護とは

「看取り」とは、病状の回復が見込めず死が近くに迫っている状況の方に対して、最期のときまで見守ることをいいます。看取り介護では無理な延命治療などは行わず、苦痛を緩和するケアを行い、その方らしい最期が迎えられるように支援します。
人生の最終段階において最期を迎えたい場所
厚生労働省の「令和4年度 人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」の中で、「人生の最終段階において、最期を迎えたい場所」についてのアンケート結果は状況別に以下の結果でした。
| 最期のときを迎える状態 | 医療機関 | 介護施設 | 自宅 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| 病気で治る見込みがなく、およそ1年以内に死に至ると考えたとき | 34.7% | 9.1% | 52.6% | 3.6% |
| 末期がんと診断され、痛みはないが呼吸が苦しい状態のとき | 44.1% | 12.2% | 42.8% | 0.9% |
| 慢性の重い心臓病と診断され、痛みはないが呼吸が苦しい状態のとき | 45.7% | 12.2% | 40.6% | 1.4% |
| 認知症と診断され、自分の居場所や家族の顔が分からない状態のとき | 18.2% | 64.2% | 16.2% | 1.4% |
1年以内に死に至る状況の場合には、半数以上の方が最期のときを自宅で過ごしたいと考えていることがわかりました。がんや心臓病と診断された場合には、何らかの医療処置が必要なことも考えて、医療機関での最期を考える方が増えますが、それでも40%以上の方が自宅での最期を望んでいます。
1年以内に死に至る状況の場合に、自宅で最期を迎えたいと思う理由の上位は以下の通りです。
- 住み慣れた場所で最期を迎えたいから
- 最期まで自分らしく好きなように過ごしたいから
- 家族等との時間を多くしたいから
- 家族等に看取られて最期を迎えたいから
一方で、自宅以外で最期を迎えたい方は「介護してくれる家族等に負担がかかるから」「症状が急に悪くなったときの対応に自分も家族等も不安だから」という理由が上位を占めています。
参考:厚生労働省「令和4年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」
医療ケアを望む場合
終末期に行う医療ケアを「ターミナルケア」と言い、日本語でいうと「終末期医療」「終末期看護」を意味します。単なる「看取り介護」の場合は、日常の介護が中心ですが、ターミナルケアでは、胃ろうなどの経管栄養・酸素吸入・人工呼吸器などの医療ケアを施します。
また「緩和ケア」も医療ケアを行う終末期の支援です。がんなどによる痛みの緩和や症状の管理、精神的苦痛をやわらげる治療を並行しながら支援します。
積極的な医療処置を希望するかしないかによって受けるケアは異なりますが、いずれにしてもその方らしく最期を迎えるためのケアに変わりはありません。症状によっては、自宅で往診や訪問看護サービスを利用しながら緩和ケアを受けることも可能です。
訪問介護事業所が看取り期に説明しておくべきこと

看取り介護では、ご本人やご家族が納得した最期が迎えられるように、充分な話し合いや説明が大切です。どのような説明が必要になるのか確認しておきましょう。
国が定める終末期医療の決定プロセスガイドライン
平成19年に厚生労働省により「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」が提示されました。
ガイドラインには、終末期医療及びケアの在り方が以下のように示されています。
- 医療従事者が適切な情報の提供と説明を行い、それに基づく話し合いにより患者本人による決定を基本として終末期医療を進める
- 医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止等は、多専門職種から構成される医療・ケアチームによって慎重に判断する
- 可能な限り疼痛や不快な症状を緩和し、精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行う
充分な説明のうえ、ご本人やご家族により意思決定してもらうことが大切です。
参考:厚生労働省「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」
医師による説明(インフォームド・コンセント)
インフォームド・コンセントとは「説明と同意」のことです。医療を受ける際には、医師などの医療従事者から病状や治療について説明を受け、充分に理解した上で自らが納得した選択を行うことができます。医療従事者の説明する方針に同意することで治療が決定します。
在宅での看取りは医療機関と異なり、受けられる治療が限られるためインフォームド・コンセントが重要です。手厚い医療サービスは提供できないことや、医療処置・延命措置は基本的に行わないことに対して意思をしっかり確認しておかなければなりません。
これらの説明を受けたうえで、在宅での看取りを希望する場合に文書を交わし医師と患者双方で保管します。ケアの方針はあとから変更できるため、状態が変わった場合に介護施設への入所や医療機関への入院を選択することも可能です。
訪問介護で対応できることを説明
在宅での看取りを希望された場合には、ケアマネジャーが中心となり介護保険サービスを調整します。このときケアマネジャーが作成するのがケアプランです。
サービス提供責任者はケアプランをもとに訪問介護計画書を作成し、その計画書にご本人やご家族から同意をいただきます。その際には、ヘルパーが対応できるケアの内容や緊急時の対応など、訪問介護事業所としてできることとできないことをしっかりと説明しておきましょう。
ケアプランには、ご本人の心身の状態やご家族の介護状況に応じて訪問介護だけでなく、訪問看護・訪問入浴・福祉用具などさまざまなサービスが組み込まれています。それぞれのサービスと連携しながらご利用者とご家族を支えていくことになります。
看取り介護でヘルパーができること

看取りケア期に訪問介護で行われる援助内容を確認しておきましょう。
身体的ケア
看取り期になると、身体介護はベッド上で行うことが多くなります。安心・安楽に配慮しながらケアを行っていきましょう。
食事・水分摂取
看取りの時期は徐々に食事や水分の摂取量が減っていき、やがて食べられなくなっていきます。咀嚼や嚥下がしやすいように、きざみ食やペースト食などに食事形態を変更すると摂取しやすくなります。とくに水分摂取が大切なので、むせるようならとろみをつけるなどの工夫も必要です。
ただし、この時期には無理に食事をすすめるようなことはしません。好きなものを好きなだけ食べていただくことが大切です。
清潔の保持
ベッドから体を起こせない場合、浴槽を自宅内に持ち込み、寝た状態のままで入浴ができる訪問入浴を利用することがあります。また、清拭のみで対応することもあります。入浴は体に負担がかかってしまうため、体調に注意しながら実施しなければなりません。医療スタッフと相談しながら清潔保持の方法を検討していきます。
また、心地よく過ごせるように着替えやシーツ交換をこまめに行い、衣服や寝具を清潔な状態に保っておくことや、口腔ケアなども重要です。とくに口の中が汚れていると細菌により誤嚥性肺炎を起こすリスクが高まります。
排泄介助
歩行が困難になったり体が起こせなくなったりすると、トイレで排泄するのが困難になり、ポータブルトイレを使用する方やおむつで排泄する方が増えます。排尿困難になりバルーンカテーテルを使用する方もいます。排泄介助では尿路感染症をおこしたり、皮膚トラブルから褥瘡を発症したりしないように清潔保持に注意しなければなりません。
また、下痢や便秘の状態や尿量によっても健康状態が観察できます。排泄物や皮膚状態の観察にも注意を向けながらケアを行いましょう。
苦痛の緩和・安楽な姿勢の保持
症状には個人差がありますが、倦怠感・発熱・気分不良などの苦痛を伴うことが多くなります。できるだけ苦痛を取り除けるようにクーリングやマッサージ、安楽な姿勢の保持などに配慮することが大切です。とくに寝たきりの状態が続くと、体を動かせずに同じ箇所ばかり圧迫されて褥瘡ができるリスクが高まります。エアマットの利用や、定期的な体位交換も重要です。
状態観察・記録・報告
看取り期は食事摂取量・水分摂取量・バイタル測定値・尿量・排便量など体調の変化をこまめに記録に残すことが大切です。しっかりと記録することで、次にケアに入るスタッフや医療従事者に現在の状況を申し送ることができます。とくに、いつもと違う状態に気づいた時には記録とともに速やかに報告するようにしましょう。
精神面のケア
死期がせまると死に対する不安や恐怖に襲われることは想像に難くありません。看取り期は精神的なサポートも重要です。
気持ちに寄り添うコミュニケーション
不安感や孤独感を少しでも軽減できるように話を聞く・こまめな声掛けをする・体をさすったり手を握ったりスキンシップをはかるなど、コミュニケーションを大切にしましょう。耳は最期まで聞こえていると言われます。安心できるように優しい声掛けをして苦痛を和らげるような精神的なサポートも大切な支援です。
環境整備
快適に過ごせる環境を保つために、適度な室温や湿度の調節や換気にも気を配ります。最期まで人としての尊厳を守るために、プライバシーを尊重することも重要です。また、最期の時をご家族とゆっくり過ごせるように配慮することも大切です。
家族のサポート
看取り介護はご家族の体や心にも大きなストレスがかかります。そのため、休息できるように配慮したり、気持ちに寄り添うお声がけを行います。ご家族の負担を少しでも軽減できるようなサポートを心がけましょう。
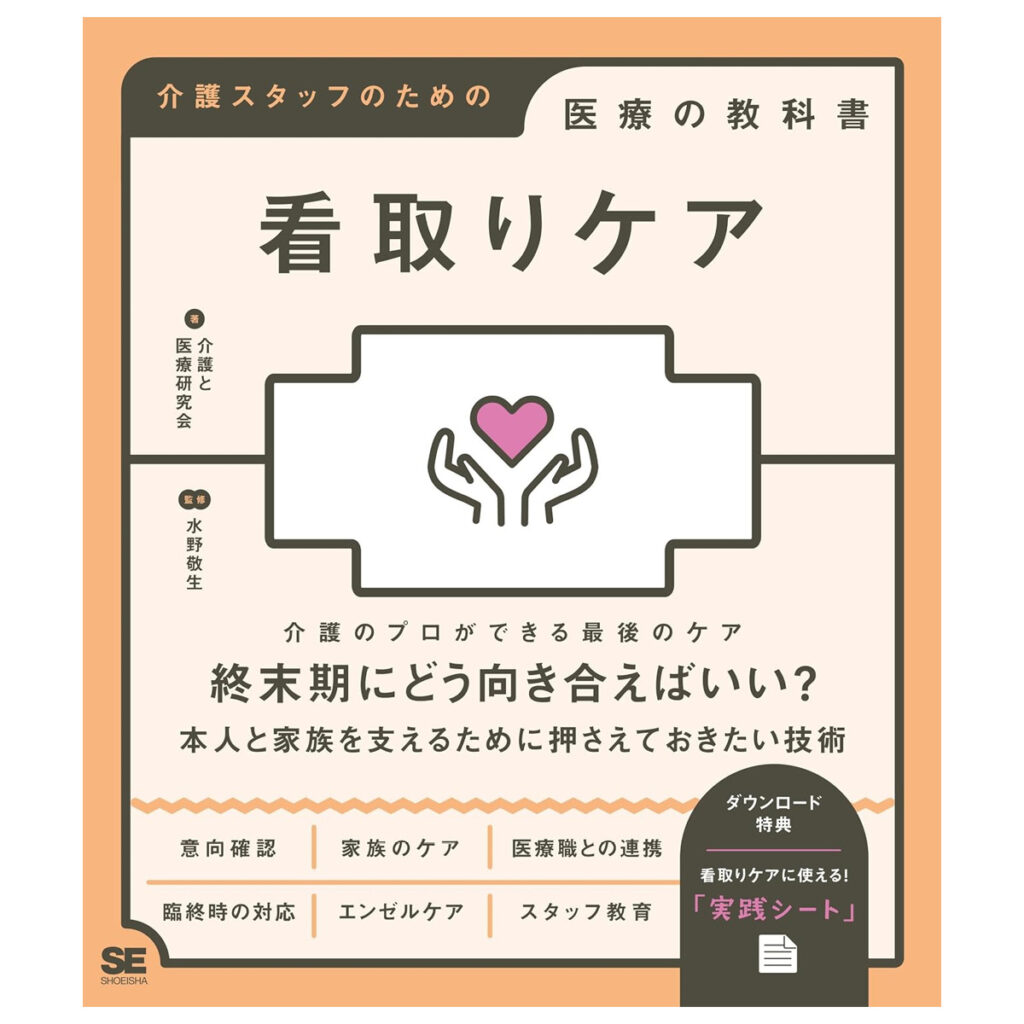
看取りケア 介護スタッフのための医療の教科書
終末期にどう向き合えばいい?
本書では事前の意向確認、臨終時の対応、医療職との連携など、看取りに関する知識と技術が実際の流れに沿って解説されています。
遺族への接し方や、近年増加している在宅での看取りにも対応。介護職として入所者の終末期にどう向き合うか、知っておきたい情報が詰まった一冊です。
看取りケアは丁寧な説明と連携が重要

今回の記事では「在宅での看取り介護で必要な説明やヘルパーが気をつけること」と題して解説しました。看取り介護の際は、とくにご本人やご家族としっかりコミュニケーションをとることが大切です。ケアに対する丁寧な説明で意思疎通を図ることが信頼につながります。
訪問介護事業所として看取り期にできること、気を付けておきたいことを、今一度スタッフと共有しておきましょう。
きめ細やかな訪問記録はテレッサモバイルがおすすめ

看取り期はこれまで以上に細やかな様子観察を行い、適切に報告する必要があります。記録をスムーズに行うために、訪問介護の記録に特化した「テレッサモバイル」を導入してみてはいかがでしょうか。テレッサモバイルは、LINEを使用した介護記録管理アプリです。ヘルパーさんは、サービス実施記録をLINEで送信、リアルタイムで記録をサ責に報告できます。
こまめな報告やスケジュール変更が必要になる看取り期にも役立つはずです。最大2カ月無料でお試しできますので、ぜひ検討してみてください。
投稿者プロフィール

-
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則
お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則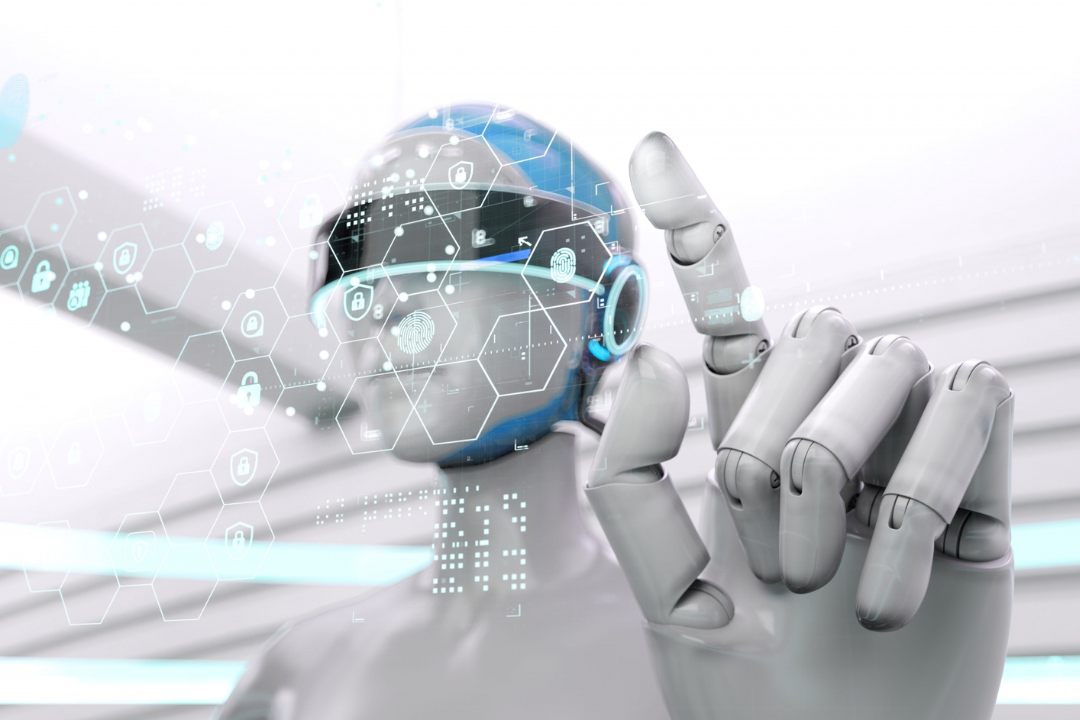 コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント
コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方
お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方 お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ
お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ