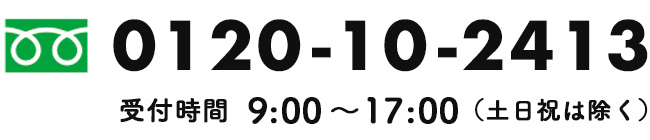利用者や家族から訪問介護の料金について質問された時、正確で分かりやすい説明ができているでしょうか?
訪問介護の料金は、サービス内容と利用時間によって決まる複雑な仕組みで、加算や軽減制度も含めて正確に理解することが重要です。
この記事では、料金体系の基本から要介護度別の具体的な費用例、さらに利用者負担を軽減する制度まで、実際の説明場面で活用できる実践的な情報をお伝えします。
訪問介護の料金体系を詳しく解説

訪問介護の料金は、国が定める単位数に基づく算定方式により決定されます。単位数、地域区分、自己負担割合、各種加算の組み合わせで最終的な利用者負担額が確定するため、これらの仕組みを体系的に理解することが重要です。
単位数算定と地域単価の基本ルール
訪問介護の利用料金は、介護報酬の「単位数」に基づいて計算されます。この単位数は、サービスの種類や提供時間によって厚生労働省が定めており、「身体介護」と「生活援助」「通院等乗降介助」で区分が異なります。
さらに「地域区分」という考え方があり、人件費や物価の違いを反映するため、全国を1級地から7級地、その他に分けた8つの区分に分類しています。たとえば、東京都特別区などの1級地では、1単位あたり11.40円、物価が比較的安い地域では10.00円といった地域単価が設定されています。
実際の料金計算では、「単位数×地域単価」で1回あたりのサービス費用が算出されます。このように、同じサービス内容でも地域によって料金が異なるのが特徴です。
サービス内容別の料金設定
訪問介護の料金は、身体介護、生活援助、通院等乗降介助の3種類で異なる単位設定となっています。
身体介護の単位数
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 20分未満 | 163単位 |
| 20分以上30分未満 | 244単位 |
| 30分以上60分未満 | 387単位 |
| 1時間以上 | 567単位に30分を増すごとに82単位を加算 |
生活援助の単位数
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 20分以上45分未満 | 179単位 |
| 45分以上 | 220単位 |
| 身体介護(20分以上)に引き続き生活援助を行った場合 | 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに65単位を加算(※195単位を限度) |
通院等乗降介助・その他
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 1回につき(片道) | 97単位 |
身体介護と比較して生活援助の単位数が低く設定されているのは、専門性の違いと提供内容の特性を反映したものです。
自己負担割合の決まり方
利用者が実際に支払う金額は、所得に応じて1割、2割、3割のいずれかの負担割合が適用されます。
1割負担は介護保険制度の基本的な負担割合で、大部分の利用者がこの1割負担に該当します。現役並みの所得がある場合は、所得水準に応じて2割から3割の負担割合です。
自己負担割合は要介護認定で要介護や要支援の判定が下りるときに決定され、「介護保険被保険者証」と一緒に負担割合が記されている「介護保険負担割合証」も郵送されます。以降は毎年7月に更新され、各市町村から郵送で交付されるので、事業所への提示が必要です。
加算料金が発生するケースと内容
訪問介護では、基本料金に加えて特定の条件を満たした場合に加算料金が発生します。主な加算の種類と内容は以下の通りです。
【代表的な加算の種類と算定条件】
| 加算名 | 単位数・加算率 | 算定条件 |
|---|---|---|
| 初回加算 | 1月につき200単位 | 新規利用者に対してサービス提供責任者が初回訪問または他のホームヘルパーに同行した場合 |
| 2人の訪問介護員等による場合 | 所定単位数の200% | 利用者の状況により、2人の訪問介護員が、1人のご利用者に対して介護サービスを提供した場合 |
| 緊急時訪問介護加算 | 1回につき100単位 | 利用者や家族からの要請でケアマネジャーが必要と認めた緊急的な身体介護を提供した場合 |
| 特定事業所加算 | 基本報酬の3%~20% | 人材要件、重度要介護者対応要件、サービス提供体制強化要件などを満たした事業所 |
【時間帯加算】
| 時間帯 | 加算率 |
|---|---|
| 夜間早朝(18時~22時、6時~8時) | 基本報酬の25%増し |
| 深夜(22時~6時) | 基本報酬の50%増し |
上記以外にも、介護職員処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算、同一建物減算など、事業所の体制や利用状況に応じてさまざまな加算・減算があります。
これらの加算は事業所の体制やサービス提供状況により適用の有無が決まるため、契約時に詳細を確認することが重要です。
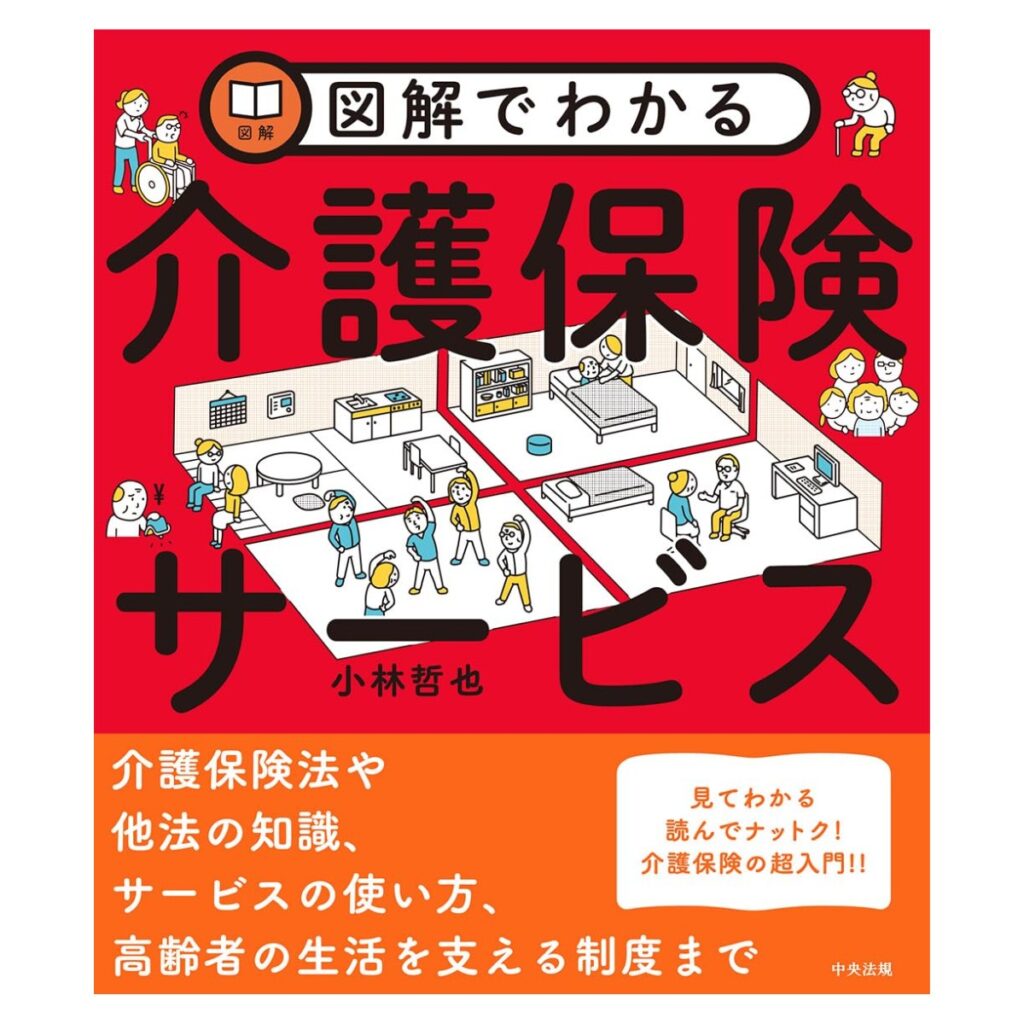
図解でわかる介護保険サービス
高齢者をとりまく課題から、介護保険制度や介護保険サービス、その他関連制度の知識をわかりやすく解説。豊富な図とイラストで視覚的に理解できる構成。介護保険サービスの従事者や新人職員、ケアマネ等の相談援助職など、高齢者支援にかかわるあらゆる方にオススメ。
要介護度別の月額費用シミュレーション

訪問介護の月額費用は、要介護度やサービス利用頻度により大きく変動します。実際の利用パターンを想定した具体例により、利用者への説明時に参考となる費用算定方法を示します。
要介護1の方の利用例と月額費用
要介護1の方は、比較的軽度の介護が必要で、部分的な生活支援が中心となります。
【利用例:Aさん(要介護1)の場合】
- 週2回の生活援助(45分以上、調理と掃除)
- 週1回の身体介護(30分以上60分未満、入浴介助)
【月額費用の計算】
| サービス内容 | 単位数 | 利用回数/月 | 月間単位数 |
|---|---|---|---|
| 生活援助(45分以上) | 220単位 | 8回 | 1,800単位 |
| 身体介護(30分以上60分未満) | 387単位 | 4回 | 1,552単位 |
| 合計 | 3,352単位 |
【自己負担額(地域単価10円、1割負担の場合)】
- 月間単位数:3,352単位
- 地域単価:10円
- 自己負担割合:1割(10%)
この費用水準は、家計への負担が比較的軽微でありながら、必要な介護支援を受けることで在宅生活の継続と要介護度の進行予防につながる重要な投資といえます。
要介護3の方の利用例と月額費用
要介護3の方は、中重度の介護が必要で、身体介護の頻度と時間が増加します。
【利用例:Bさん(要介護3)の場合】
- 週3回の生活援助(45分以上、調理・掃除)
- 毎日の身体介護(30分以上60分未満、食事・入浴・排泄介助)
【月額費用の計算】
| サービス内容 | 単位数 | 利用回数/月 | 月間単位数 |
|---|---|---|---|
| 生活援助(45分以上) | 220単位 | 12回 | 2,640単位 |
| 身体介護(30分以上60分未満) | 387単位 | 30回 | 11,610単位 |
| 合計 | 14,250単位 |
【自己負担額(地域単価10円、1割負担の場合)】
- 月間単位数:14,250単位
- 地域単価:10円
- 自己負担割合:1割(10%)
この段階では日常生活全般にわたる支援が必要となり、在宅生活継続のために不可欠な費用水準となります。
要介護5の方の利用例と月額費用
要介護5の方は、最重度の介護が必要で、長時間かつ頻回のサービス利用となります。
【利用例:Cさん(要介護5)の場合】
- 週2回の生活援助(45分以上)
- 1日3回の身体介護
- 朝:30分以上1時間未満
- 昼:20分以上30分
【月額費用の計算】
| サービス内容 | 単位数 | 利用回数/月 | 月間単位数 |
|---|---|---|---|
| 生活援助(45分以上) | 220単位 | 8回 | 1,760単位 |
| 身体介護(30分以上60分未満)朝 | 387単位 | 30回 | 11,610単位 |
| 身体介護(20分以上30分未満)昼 | 244単位 | 30回 | 7,320単位 |
| 合計 | 20,690単位 |
【自己負担額(地域単価10円、1割負担の場合)】
- 月間単位数:20,690単位
- 地域単価:10円
- 自己負担割合:1割(10%)
要介護5の支給限度基準額は36,217単位であり、この利用例は限度額内です。ただし、訪問看護、デイサービス、ショートステイなど他サービスの利用や加算項目によっては超過する場合があるため注意が必要です。

図解でまるわかり! 2024年4月介護保険改正ガイド
2024年4月の介護保険制度改正について、サービス別に図版を交えてわかりやすく解説。
介護報酬や運営基準の変更点のほか、診療報酬、障害福祉サービスの報酬改定も網羅。
制度内容を押さえておくのに相談援助職、介護職必携の一冊。
利用者負担を軽減する制度と申請方法

訪問介護の利用料が高額になった場合、軽減制度を活用することで自己負担を大幅に削減できます。これらの制度を適切に理解し、利用者に情報提供することで、経済的な理由でサービス利用を諦める状況を防ぐことができます。
高額介護サービス費による月額負担の上限設定
高額介護サービス費は、同じ月に支払った介護サービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が後から払い戻される制度です。
| 所得区分 | 月額負担上限額(世帯) |
|---|---|
| 生活保護受給者 | 15,000円 |
| 非課税世帯(年金等収入80万円以下) | 個人15,000円・世帯24,600円 |
| 非課税世帯(一般) | 24,600円 |
| 一般課税世帯 | 44,400円 |
| 現役並み所得(課税所得380万円以上) | 93,000円 |
| 高所得世帯(課税所得690万円以上) | 140,100円 |
※「非課税世帯(年金等収入80万円以下)」は、前年の公的年金等収入とその他所得の合計が80万円以下の場合です。
申請方法
- サービス利用月の翌々月に、市区町村から申請書が送付されます。
- 初回のみ申請手続きが必要です。必要事項を記入し、提出します。
- 2回目以降は自動的に指定口座へ振り込まれます。
- 世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合算で計算されます。
申請書の提出方法や必要書類は自治体によって異なる場合があるため、詳細はお住まいの自治体でご確認ください。
社会福祉法人軽減制度による低所得者の負担軽減
社会福祉法人軽減制度は、低所得で生活困窮と認められた方の利用者負担を軽減する制度です。
対象となる方の条件
社会福祉法人軽減制度を利用できるのは、主に以下の条件を満たす方です。
- 世帯全員が住民税非課税であること
- 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに+50万円)
- 預貯金が単身世帯で350万円以下(世帯員1人増ごとに+100万円)
- 日常生活に使っていない資産がないこと
- 扶養できる親族がいないこと
- 介護保険料の滞納がないこと
※市区町村によって細かい基準が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。
軽減割合
対象者は、自己負担額が以下のように軽減されます。
| 対象者 | 軽減割合 | 軽減後の自己負担 |
|---|---|---|
| 老齢福祉年金受給者 | 2分の1軽減 | 利用者負担の50% |
| その他の対象者 | 4分の1軽減 | 利用者負担の75% |
この制度は、社会福祉法人などが運営する事業所でのみ利用可能です。すべての介護サービス事業所が対象ではないため、利用を希望する場合は必ず事前に確認しましょう。また、軽減が適用される期間は原則1年間です。継続して利用したい場合は、再度申請が必要です。
申請方法
申請は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で行います。申請時には、収入や資産状況を証明する書類が必要です。認定されると「軽減確認証」が交付され、対象のサービス利用時に提示します
高額医療・高額介護合算制度による年間負担の軽減
高額医療・高額介護合算制度は、医療費と介護サービス費の自己負担を合算し、1年間の合計が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。
【年間自己負担限度額(70歳以上)】
| 所得区分 | 年間限度額 |
|---|---|
| 一般所得者 | 56万円 |
| 低所得2(非課税) | 31万円 |
| 低所得1(非課税) | 19万円 |
申請方法
- 申請先:加入している医療保険の保険者(市区町村・健康保険組合等)
- 申請時期:毎年7月31日が基準日(8月以降に申請)
- 必要書類:自己負担額証明書(介護保険分)、医療費の領収書等
この制度は医療と介護の両方を利用している方にとって、年間の負担軽減効果が大きい重要な制度です。
訪問介護事業所の選び方と料金の注意点

適切な訪問介護事業所の選択は、サービス品質と料金負担の両面で重要な判断となります。事業所選びでは、基本料金に加えて特定事業所加算の取得状況を確認しましょう。加算取得事業所は手厚いサービス体制を整えている反面、利用料が高くなります。
また、サービス提供時間の計算方法や地域区分の適用についても事業所により異なるため、正確な料金を事前に確認しておくことが大切です。キャンセル料、自費サービスなど、保険適用外の実費負担についても、契約前に必ず確認し、予期せぬ費用負担が発生しないようにしましょう。
訪問介護の料金を正しく理解して適切な利用者支援を

訪問介護の料金は、単位数、地域区分、自己負担割合、加算の組み合わせで決まる複雑な仕組みです。利用者への正確な料金説明と軽減制度の活用提案により、経済的な不安を解消し、安心してサービスを利用していただけるようにしましょう。
訪問介護の記録作成や請求業務でお困りではありませんか?テレッサモバイルは、訪問介護に特化した介護記録管理アプリです。LINEを使用したシンプルなシステムで、サービス記録が一元管理できるので、サービス提供責任者の業務負担を大幅に軽減します。
ぜひ無料お試しを検討ください。
こちらの記事もおすすめ
投稿者プロフィール

-
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則
お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則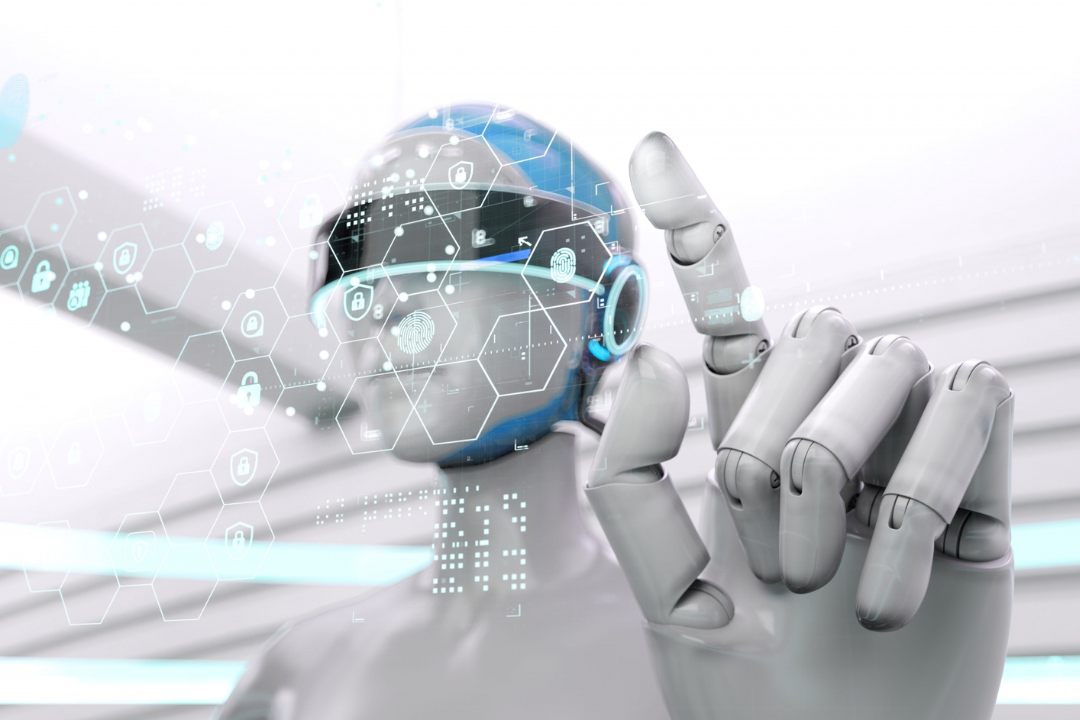 コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント
コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方
お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方 お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ
お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ