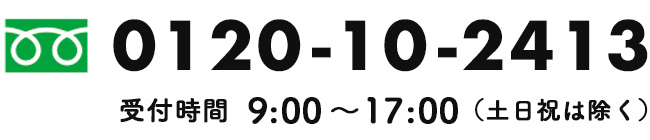高齢の家族を在宅で介護する際、適切なサービス選びはとても重要です。「訪問介護」と「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の特徴や違いを知ることで、それぞれの家庭に合った支援を選びやすくなります。
本記事では、サービス内容や料金体系、メリット・デメリットなどを比較し、家族のニーズに合った最適な介護サービスの選び方を解説しますのでぜひ参考にしてください。
訪問介護と定期巡回サービスの基本概要

訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、いずれも自宅で受けられる介護保険サービスです。しかし、提供時間や対応体制、目的には明確な違いがあります。ここでは、それぞれの概要と目指す役割について解説します。
訪問介護とは?
訪問介護は、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行うサービスです。サービスはケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて提供され、訪問の頻度や時間、支援内容があらかじめ決められています。具体的には、入浴・排泄・食事などの身体介護に加え、掃除・洗濯・買い物といった生活援助が含まれます。
1回のサービス時間は30〜60分程度で、週1回から毎日まで柔軟に設定されます。ただし、訪問介護でも夜間や早朝の対応は加算対象として提供可能な場合がありますが、対応できる事業所や体制には限りがあるのが現状です。
また、緊急時の呼び出しには対応できないことも多く、体調の急変や安否確認が必要な場面では限界が生じることがあります。そのため、在宅介護を担う家族の負担が大きくなる可能性があります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問介護に加えて、24時間体制での巡回・緊急対応・看護支援がセットになった包括的な介護サービスです。あらかじめ決められた時間帯に定期訪問を行うとともに、利用者からのコールやセンサー反応に応じて随時訪問や電話支援が行われます。
このサービスでは、オペレーターが常駐する拠点が中心となって利用者の状態を把握し、必要に応じてヘルパーや看護師が自宅を訪問します。たとえば、夜間にトイレ介助が必要になった場合や、転倒した際の対応など、状況に応じた柔軟なサービス提供が可能です。
定期巡回サービスは、要介護度が高い方や独居の高齢者、夜間の介護不安が強い家庭にとって、在宅生活の継続を支える大きな支援となります。医療的な対応が必要な場合には、訪問看護との連携も行われるため、介護と医療の連携体制が整っている点も特徴です。
訪問介護と定期巡回の費用の考え方

介護サービスを選ぶ際には、サービス内容だけでなく、利用にかかる費用と介護保険の適用範囲を把握しておくことが重要です。
訪問介護の料金と自己負担額
訪問介護の利用料金は、サービスの種類(身体介護・生活援助)、提供時間、訪問回数によって異なり、30分単位や60分単位などで細かく設定されています。
たとえば、30分の身体介護を1回受けた場合、保険適用後の自己負担額は数百円程度となります。ケアプランに沿って決められた回数・内容を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担になるため注意が必要です。
また、訪問介護では、夜間や早朝、祝日・年末年始などの加算料金が発生する場合もあります。事業所によってはキャンセル料が別途かかることもあるため、事前の確認が欠かせません。費用の見通しを立ててから契約することで、家計への影響を抑えることができます。
定期巡回サービスの月額制と費用感
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、月額制を基本としたサービス形態で、1カ月あたりの利用回数や訪問時間にかかわらず、一定額の費用で24時間の支援が受けられるのが特徴です。利用者にとっては、回数を気にせず必要な時に何度でも介護を依頼できる点が大きな利点です。
月額料金は要介護度に応じて段階的に設定されており、要介護度が高いほど利用単価も高くなります。訪問回数が多い方や、夜間・緊急対応が必要な方にとっては、従来の訪問介護よりも費用対効果が高いと感じるでしょう。
この月額制により、突発的なニーズや頻繁な介護が求められる状況でも予算管理がしやすくなり、介護費用の安定化につながります。
サービス内容の具体的な違い

訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、提供されるサービスの範囲や柔軟性にも明確な違いがあります。ここではそれぞれのサービス内容の違いを比較していきます。
身体介護・生活援助の範囲
訪問介護と定期巡回サービスは、いずれも身体介護や生活援助を基本としたサービスを提供しています。ただし、その運用方法や対応の柔軟性には違いがあります。
訪問介護では、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、決まった時間帯にあらかじめ設定された支援を提供します。入浴、排泄、食事などの身体介護や、掃除、洗濯、買い物といった生活援助が中心で、利用者の生活リズムに合わせて計画的に支援が行える点が強みです。一定の時間内で効率的なサービス提供が可能なため、家庭内での介護計画が立てやすいというメリットもあります。
一方で定期巡回サービスは、定時訪問に加え、緊急時にはオペレーターの判断により随時訪問が行える体制が整っています。これにより、急な体調不良や夜間の介助など、予測できない事態にも対応しやすくなっています。
定期巡回の即応性と、訪問介護の計画性と継続性、それぞれの特性を理解したうえで、利用者と家族にとって最も負担の少ないかたちを見極めることが重要です。
通院等乗降介助や見守り支援
訪問介護には「通院等乗降介助」と呼ばれるサービスがあります。これは、通院などで外出する際に、玄関から車まで、車から病院までの付き添いと乗降を介助するものです。ただし、訪問介護の範囲では、病院内での待機や診察の付き添いなどは対象外であり、事前に申請と認定を受けていないと利用できないこともあります。
定期巡回サービスでは、通院支援そのものは直接の対象外とされるケースが多いですが、外出前後の支援や移動後の見守り体制は整っています。また、訪問介護よりも対応可能な時間帯が広いため、朝早い通院の送り出しや夜間帰宅後の対応なども相談しやすい傾向があります。
さらに、「安否確認」や「見守り」を重視しており、独居高齢者や認知症のある方へのリスク管理がしやすくなっています。
訪問看護・医療連携の有無
訪問介護では、原則として医療行為は行えません。服薬の見守りや座薬の補助など、一定範囲の介助は可能ですが、注射や創傷処置などの医療行為は訪問看護に委ねられます。したがって、訪問介護を利用しながら医療的な支援が必要な場合は、別途訪問看護サービスを導入する必要があります。
一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問看護の提供が含まれており、介護と医療の連携を前提としたサービス設計です。夜間の体調変化や医療的ケアが必要な場面にも、看護師などの医療スタッフが迅速に対応できる体制が整っており、安心して在宅生活を続けられる支援が受けられます。
訪問介護と定期巡回サービスのメリット・デメリット

どちらのサービスにも利点と制限があるため、利用者や家族の状況に応じて適した選択が求められます。それぞれのサービスの長所と課題を比較し活用のポイントを整理します。
訪問介護のメリットと課題
訪問介護の大きなメリットは、必要な支援を必要な分だけ柔軟に組み合わせられる点にあります。訪問介護以外の在宅サービスと組み合わせることで、通院支援やリハビリ、福祉用具の利用など多様なサービスを取り入れることもでき、在宅介護の幅を広げることが可能です。
また、利用頻度が少ない場合はコストを抑えて利用できるため、介護度が軽度の方や家族の支援が比較的充実している世帯には適した選択肢です。サービス提供事業所も多いため、地域での選択肢が豊富なのも強みです。
一方で、訪問時間が決まっていることから、急な事態には対応が難しい場合があります。緊急時の呼び出しに対応できないケースもあるため、独居高齢者や介護度が高い方にとっては不安が残ることもあります。
また、必要な支援が増えた場合には、その都度ケアプランの見直しや訪問回数の追加による調整が必要となり、家族にとっての負担が増すことも考慮する必要があります。
定期巡回サービスの強みと注意点
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の最大の強みは、24時間365日、必要なときに対応可能な点です。日中の定時訪問だけでなく、夜間や緊急時のコールにも即時対応できる体制が整っているため、独居の高齢者や在宅での看取りが必要な方にも適しています。
介護と看護の連携が取れている事業所では、医療的なニーズにも対応可能で、複雑なケアを一体的に受けられる点も利点です。訪問回数に制限がない月額制を導入している事業所であれば、頻繁な支援が必要な場合でもコスト管理がしやすくなります。
ただし、提供地域や実施事業所の数が限られており、すべての地域で利用できるとは限りません。さらに、要介護度が低い方にとっては、月額制の費用負担が割高になる可能性があります。サービス内容や訪問頻度に対して適切な利用がなされない場合、かえって非効率になることもあるため、導入前の詳細な説明と納得感が重要です。
家族に最適な介護サービスを選ぶために

訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、いずれも在宅での介護生活を支える重要なサービスです。それぞれの特徴や仕組み、提供時間、費用面を把握し、家族のニーズや生活状況に照らし合わせて選ぶことが、後悔のないサービス利用につながります。
最終的なサービス選びは、ケアマネジャーとの相談を通じて慎重に行いましょう。サービスの違いを正しく理解し、納得できる形で介護の選択を進めていくことが、家族にとっても利用者本人にとっても、より良い生活を支える第一歩となります。
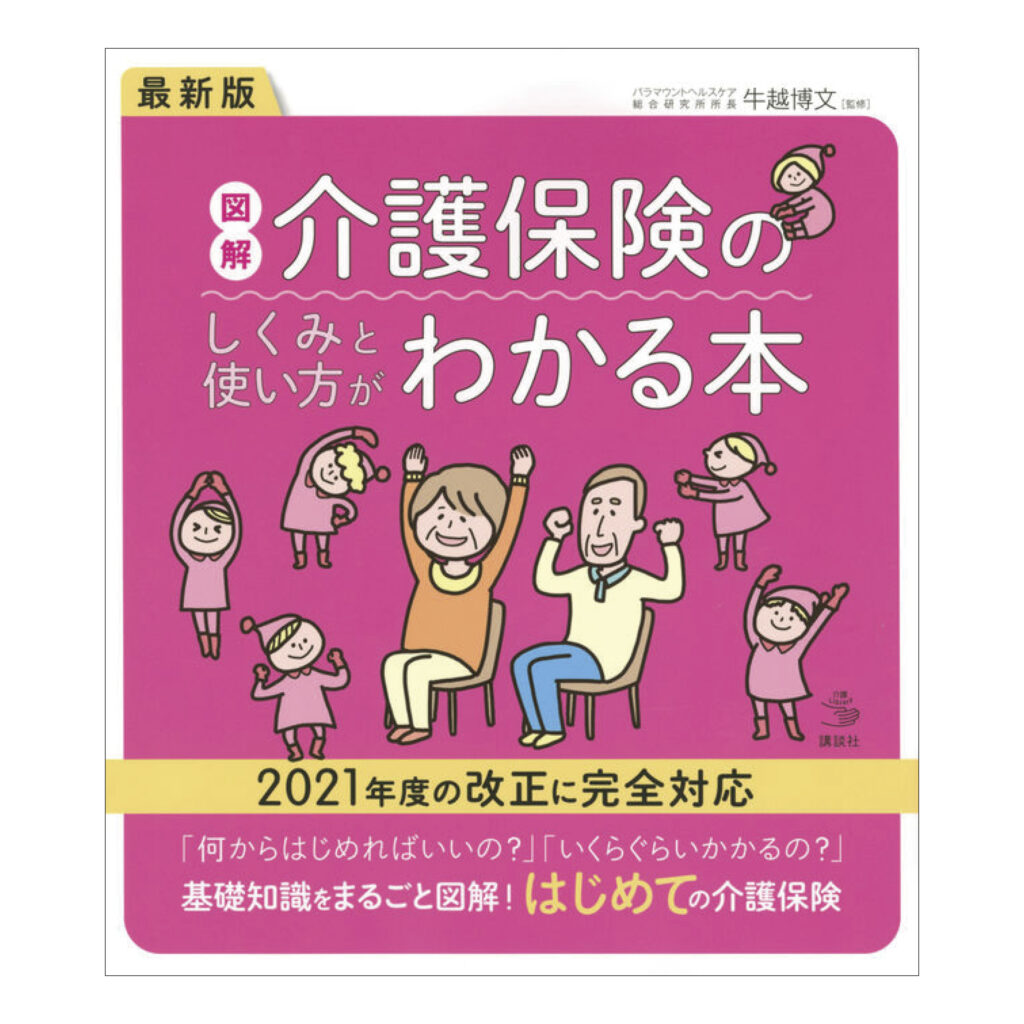
図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本
申請の仕方、ケアマネの探し方、ケアプランの作り方、介護保険で受けられるサービス、お金の話、介護保険で入れる施設など複雑な介護保険のしくみと使い方がわかります。
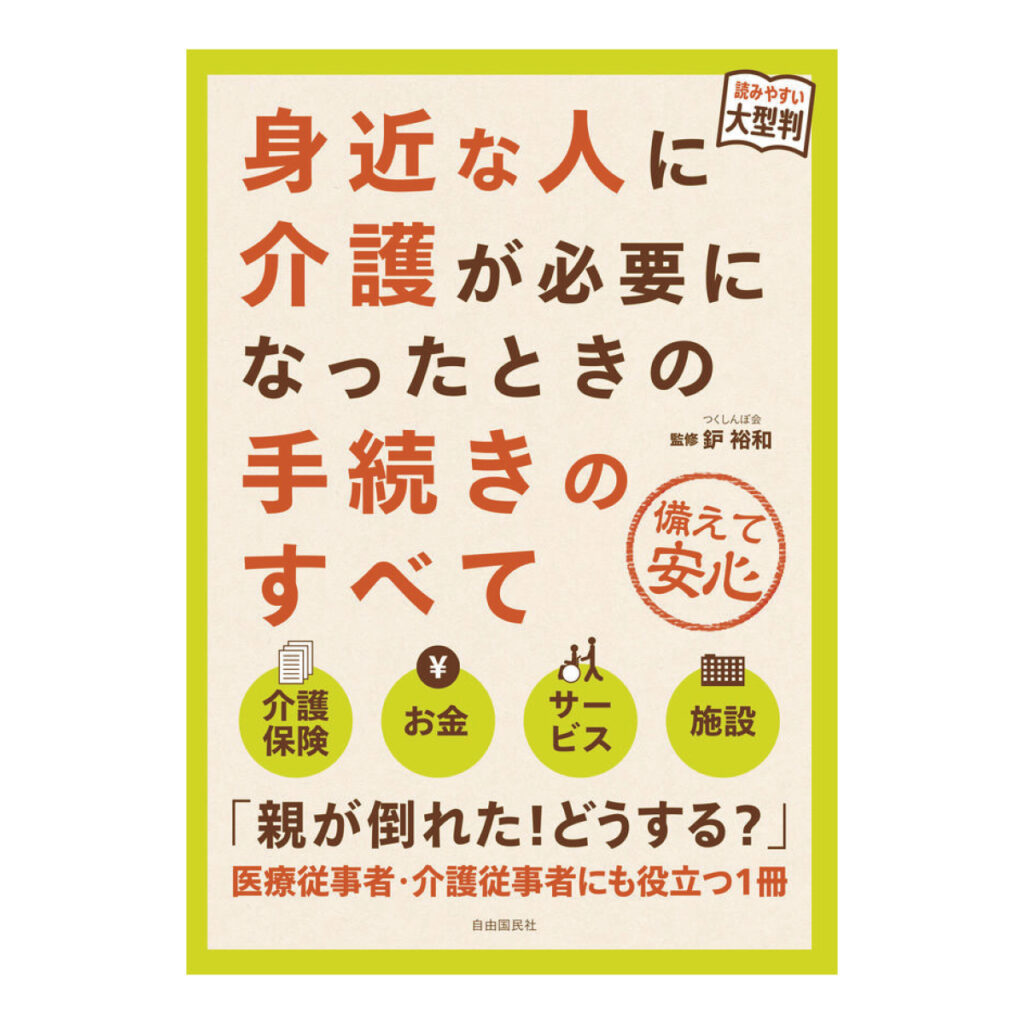
身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて
親が倒れた! どうする?
どこに相談すればいいの?申請はどうしたらいいの?施設選びは?在宅介護をするには?
不安を一気に解消してくれる1冊。
見やすく、読みやすい大判サイズです。
投稿者プロフィール

-
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則
お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則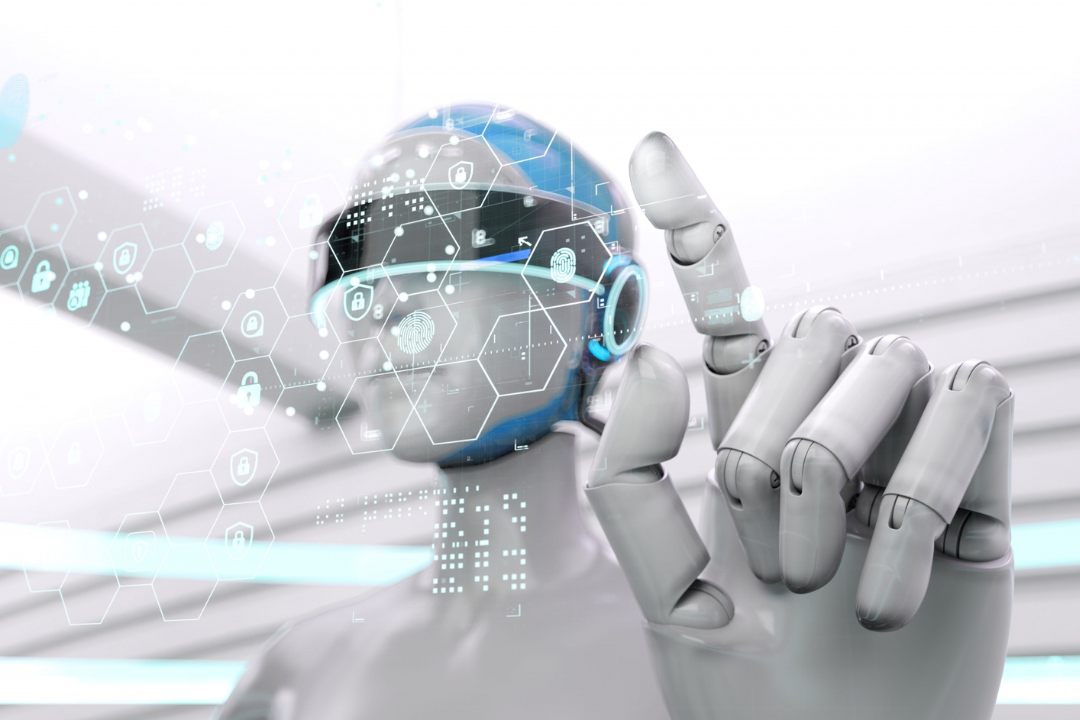 コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント
コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方
お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方 お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ
お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ