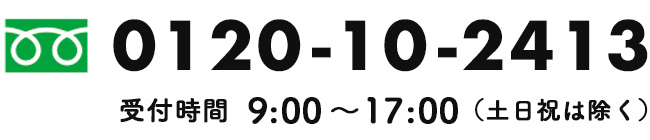サ責(サービス提供責任者)の仕事に疲弊していないでしょうか?
現在サ責として働く方も、これから目指したい方も、忙しい業務をこなすことに不安を感じる方も少なくないでしょう。
今回の記事では、サ責の仕事内容と仕事をぐっとラクにする仕事術について解説します。業務改善を検討している方はぜひ参考にしてください。
サ責(サービス提供責任者)とは?

サービス提供責任者とは一般的に「サ責」と呼ばれ、訪問介護事業所に配置が義務付けられている職種の一つです。
ケアマネジャーの立てたケアプランをもとに訪問介護計画書を作成し、ご利用者が適切な訪問介護サービスが受けられるように調整したり、ヘルパーのマネジメントを行ったり、事業所内でリーダー的な役割を担います。
サービス提供責任者になるための資格要件
サ責は、職種につけられた名前であり「サービス提供責任者」という資格や研修があるわけではありません。ただし、訪問介護事業所では中心的な役割を果たす専門職なので、サ責になるには介護職としての資格や経験が必要になります。
サービス提供責任者になるための資格要件は以下の通りです。
- 介護福祉士
- 実務研修修了者
- 旧介護職員基礎研修修了者
- 旧1級課程修了者
これまで実務経験3年以上の介護職員初任者研修修了者も認められていましたが、2019年4月以降は要件から除外されています。
サービス提供責任者の配置基準
サービス提供責任者は、訪問介護事業所に1名以上配置しなければなりません。利用者40名につき1人の配置が必要なため、40名を超えるごとに1名の増員が必要です。
ただし、以下の要件を満たしている事業所は利用者50名につき1人の配置が認められています。
- 常勤のサービス提供責任者3名以上配置されている
- サ責の業務を主として勤務する者が1名以上配置されている
- サ責業務の効率化が図られている
サ責は非常勤としての勤務も認められていますが、その場合は常勤の勤務時間の2分の1以上の稼働が要件となります。また、管理者や訪問介護員との兼務も可能です。ただし、自治体によりルールが異なるため確認が必要です。
サービス提供責任者の仕事内容

サービス提供責任者の仕事は多岐に渡りますが、主な業務は「ご利用者に関すること」と「ヘルパーに関すること」の2種類です。
1.ご利用者に関すること
サービス提供責任者は、ご利用者が訪問介護サービスを利用するにあたってトータルにサポートする役割があります。
訪問介護サービスの受付・契約
サ責はご利用者が訪問介護サービスを利用する際の受付窓口です。主にケアマネジャーから依頼を受け、サービスの利用にあたって契約などの事務的な手続きを行います。
アセスメント
サービスを開始する前にはご利用者の自宅を訪問し、アセスメントを実施します。アセスメントとは、ご利用者およびそのご家族と面談し、心身の状況や自宅の環境、介護の状況などを聞き取りすることです。どんなことに困っているのか、どんなサービスの希望があるのか、サービス内容を決める上で必要な情報を集めます。
サービス担当者会議への出席
サービス担当者会議とは、ご利用者の介護サービスについて話し合う場です。ケアマネジャーが中心となり、ご利用者・ご家族・サービス事業所の代表者など、ご利用者の介護サービスに関わるメンバーが出席し、ケアプランの内容について話し合います。
サ責は、ご利用者のより良いサービスを実現するために、訪問介護サービスの代表者としてご利用者のケアについて意見を述べます。
訪問介護計画書の作成
ケアマネジャーが作成したケアプランをもとに、訪問介護計画書を作成することもサ責の大きな役割の一つです。ケアプランやアセスメントの内容を踏まえ、サービスの具体的な内容を決定します。
援助目標やサービスの内容を計画書に示し、ご利用者やご家族に同意を得ることで訪問介護サービスの利用がスタートできます。
モニタリング
モニタリングとは、介護サービスが計画書通りに提供されているかを定期的に確認することです。
高齢者の心身の状況や生活環境は日々変化します。そのため、モニタリングを通して定期的にサービスの利用状況・心身の変化・環境の変化をチェックすることが大切です。新たなニーズに気付いた場合には、ケアマネジャーに相談しながらサービス内容の変更を検討します。
利用者や家族への連絡や相談窓口
サービス利用開始後はヘルパーが中心となり介護サービスを提供しますが、ご利用者やご家族からの連絡や相談窓口になるのはサ責です。
利用日程の変更やサービス内容に関することなど、あらゆる相談の対応を行います。クレームの対応をするケースもあるでしょう。サ責は、訪問介護事業所の代表としてあらゆる事態に対応する重要な役割を担います。
ケアマネジャーとの連携
訪問介護サービスを行う中で、ご利用者の心身の状況やニーズに変化があった場合には、サービス内容を変更しなければなりません。サービスの内容は、ケアプランに基づいて決定されるため、ケアマネジャーにはご利用者に関する情報をこまめに提供しておく必要があります。
ケアマネジャーと連携を取りながら、ご利用者のサービスを決定していくこともサ責の仕事です。
請求業務
訪問介護事業所は、サービス提供の対価として介護報酬を得ることで成り立っています。介護報酬の請求は、月末〜月初にかけてご利用者に提供したサービス実績を確認し、10日までに請求書や明細書を国保連へ送付することで支払われます。また、1割〜3割は本人負担分となるため、それぞれのご利用者にも請求しなければなりません。
ただし、事業所の規模によりサ責が担う範囲は異なります。事業所に事務職員がいる場合には、連携しながら請求業務を実施するケースが多いでしょう。
ヘルパー業務
サ責はヘルパーとして介護サービスも実施します。訪問介護員との兼務が認められているため、日常的にサービスに入るケースもあります。また、ヘルパーの急な休みに代わりが見つからなかった時の穴埋めや、困難事例・緊急時などにも対応が必要です。
2.ヘルパーに関すること
サ責のもうひとつの役割がヘルパーに関する業務です。
シフト・スケジュール調整
サ責は、ご利用者のサービスが必要な時間帯とヘルパーの希望やスキルを鑑みて全体の訪問スケジュールを作成します。サービス導入時や変更時などには、大幅なスケジュール調整が必要になる時もあります。
ご利用者の予定変更やヘルパーの急な休みなど突発的な調整が必要なケースも多いため、サ責にとっては重要な業務の一つです。
ヘルパー教育(研修・指導)
ヘルパー教育のため、研修や指導を行うのもサ責の仕事です。勉強会を開催したり入社時にオリエンテーションを行ったり、さまざまな場面で教育を行います。技術やマナーに課題があるヘルパーがいる場合には個別指導が必要なケースもあります。
また、定期的な面談や日頃の声かけなどでメンタルケアを行うことも大切です。ヘルパーが働きやすい環境づくりをするために、積極的にコミュニケーションを取ることもサ責の重要な役割です。
同行訪問
初回サービス時や新しいヘルパーが入った時などは、ご利用者のご自宅に同行し、サービスの説明や介助方法の指導、ご利用者へ紹介や顔合わせを行います。サービス導入時にサ責が同行することで、ご利用者やご家族に安心してサービスを利用していただきます。
サ責の仕事内容をラクにする仕事術

これまで説明してきたように、サ責の仕事は多岐にわたります。少しでも仕事をラクにする方法を考えて効率化することが大切です。ここからはサ責の業務をラクにする仕事術をご紹介します。
介護記録や報告のシステム化
サ責の仕事の効率化に欠かせないのが記録のシステム化です。これは必須の手段といっても過言ではないでしょう。
介護ソフトを導入することで、あらゆる情報が一元化されて業務がぐっとラクになります。システムに委ねることで、仕事が効率化できる業務の一例は以下の通りです。
介護記録
介護記録がシステム化すればヘルパーの記録が効率化するだけでなく、サ責の事務作業の負担も大幅に軽減します。他の文書と連動しているシステムであれば、同じ文章を何度も書く手間が省けます。一度作成した文章を使用して、ケアマネジャーへの報告などさまざまな場面でも活用できます。
また、ペーパーレス化はコスト削減につながり、書類を綴る手間や倉庫などの場所も取りません。過去の記録を遡りたい場合にもすぐに検索することができます。
訪問介護計画書関連
多くの介護システムではさまざまな書類が連動しているので、訪問介護計画書に関連する書類の作成も効率化できます。基本情報・アセスメント・訪問介護計画・モニタリングなどが連動していると情報を転記する必要がなく便利です。
情報共有
介護システムを利用することで、ヘルパーが日々の記録を入力するとタイムリーに情報が伝わります。わざわざヘルパーから実施記録の提出を待つ必要なく、サービスの状況が把握できます。
また、介護システムを利用すれば、自宅や出先などからでも記録を確認したり指示を出したり、あらゆることがシステムを通して行えるため情報共有がスムーズです。
国保連請求・ご利用者利用料請求
請求業務もシステム化により大幅に効率化します。実績はサービスが終了すると同時に提出されるので、実施記録用紙の提出を待つことなく請求業務に取り掛かれます。
請求関連で便利な機能は以下の通りです。
- 実績の確認
- 国保連伝送
- 介護保険証の管理
- ご利用者の請求書・領収書の発行
- 口座振替データ作成
- 入金管理
これらの機能を使えば、月末月初の請求業務はかなりラクになるでしょう。
ヘルパー管理
介護システムでは、ヘルパーのスケジュールや給与の管理も行うことができます。介護ソフト内でご利用者の訪問スケジュールが管理されているので、ヘルパーの空き情報を探して組み立てることができます。また、実施記録を入力することで稼働した時間も管理できているので、給与の自動計算や、給与明細書の発行なども簡単です。
ICTを活用したコミュニケーション
訪問介護事業所の情報共有には、コミュニケーションアプリを活用するとスムーズです。ご利用者の情報は、前述した介護ソフトの導入によりタイムリーな共有が実現します。
また、チャットツールなどを活用すれば、サ責が一人ひとりのヘルパーに連絡を入れなくても、1度送信するだけで情報共有が可能です。電話・メール・FAX・連絡ノートなどを利用した情報共有と比較すると、格段に効率化が期待できます。最近はあらゆる世代でラインなどのコミニュケーションアプリを使用している方が多いので、導入のハードルもさほど高くないでしょう。
ミーティングや研修、サービス担当者会議などはzoomなどのウェブ会議システムを導入している事業所も増えています。ウェブ会議システムを活用すれば、わざわざ集合しなくてもコミュニケーションが取れるため時間短縮につながります。サ責のテレワークが実現したり、感染症対策になったりメリットが多いので積極的にICTを活用したコミュニケーションがおすすめです。
ヘルパーを定着させる
ヘルパーの稼働が安定しなければ、サ責の業務負担は軽減しません。ヘルパーが定着しなければ、サ責がヘルパーの穴埋めで業務に入らなければならなかったり、新人研修の機会が増えたり、本来のサ責業務の時間を圧迫します。
介護業界全体が人材不足な中、訪問介護のヘルパー不足は更に深刻です。労働条件・福利厚生・採用条件を見直すほか、入社した職員が継続して勤務できるように、働きやすい職場環境作りも大切です。スキルアップできるような人材育成制度や定期的な面談によるフォローアップなど安心して勤務し続けられるように取り組まなければなりません。
多くのヘルパーに活躍してもらってこそ、訪問介護事業所の運営が安定します。職員の労働環境にも常に気を配っておくことが、サ責の仕事をラクにすることにつながります。
請求業務を外注化する
サ責の仕事の中で、特に時間がかかって大変に感じる業務が介護報酬請求業務です。毎月10日までに正しいデータを提出しなければ、事業所へ報酬が支払われないため訪問介護事業所にとっては重要な業務です。
前述の介護ソフトで大幅にラクにはなるものの、煩雑な業務も多いため請求業務は他の方に手伝ってもらうのがベストです。事務員がいる場合には手伝ってもらえますが、介護事務員を雇用する余裕がない小規模な事業所も少なくありません。そのような事業所には、代行サービスを活用する方法もあります。代行サービスを利用すれば、介護報酬請求だけを代わりに行ってもらえます。外注費だけで済むのでコストパフォーマンスは良いでしょう。
介護報酬請求だけでも外注化すれば、サ責の業務負担が軽減するだけでなく、営業やサービス向上のための取り組みに時間が使えるため、事業所の売上アップも期待できます。
サービス業者により代行してくれる業務の範囲も異なるので、検討してみるのも一つです。
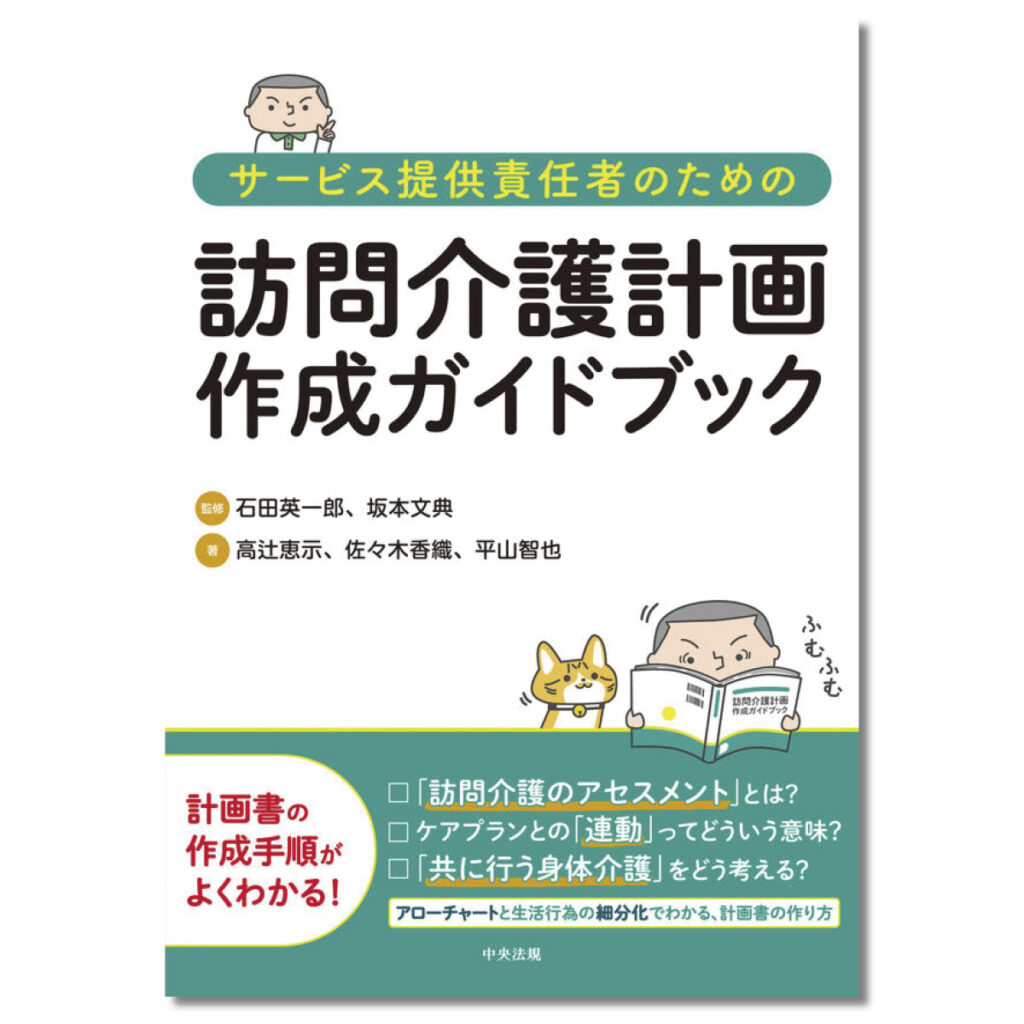
サービス提供責任者のための訪問介護計画作成ガイドブック
サービス提供責任者のための訪問介護計画作成の手順を豊富な図とイラストを使って完全解説。
さらに、10の作成事例付きで、実践でどのように応用させるかも直観的に理解できます。
「アローチャート」というアセスメント手法と「生活行為を細かく分ける視点」によって訪問介護独自のアセスメントとプラン作成の手法を説明。
訪問介護計画書を作成しやすくなる「サ責のお助けシート」も収載。
サービス提供責任者の仕事内容は多岐にわたる

今回の記事は「サービス提供責任者の仕事内容をぐっとラクにする仕事術」と題して、サ責の業務や、仕事術について解説しました。
サ責は介護職の経験を積むことにより務められる専門職です。大変な仕事ですがやりがいが得られ、今後のキャリアアップを目指す方にも最適な仕事です。これからサ責を目指す方もぜひ前向きにチャレンジしていただきたいと思います。
また、現在サ責として日々お仕事をされている方には、少しでも負担を減らしていただけるヒントになれば嬉しいです。
サ責さんの仕事の味方|テレッサモバイル

訪問介護のサ責業務をラクにするツールでお勧めしたいのが「テレッサmobile」です。テレッサmobileは訪問介護サービス実施記録をLINEで報告できるシステム。あらゆる世代で親しまれているLINEアプリを使用するので、高齢ヘルパーさんにも簡単に操作いただけると好評です。
ヘルパーさんはサービス提供後、スマートフォンから実施記録を送信でき、直行直帰が可能になり、リアルタイムで記録が送られてくるため、サ責さんもタイムリーに情報が確認できます。
最近では、多くの事業所でICT化が勧められており、サ責業務も見直されつつあります。あらゆるツールを駆使し、快適に働ける環境を目指しましょう。
投稿者プロフィール

-
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則
お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則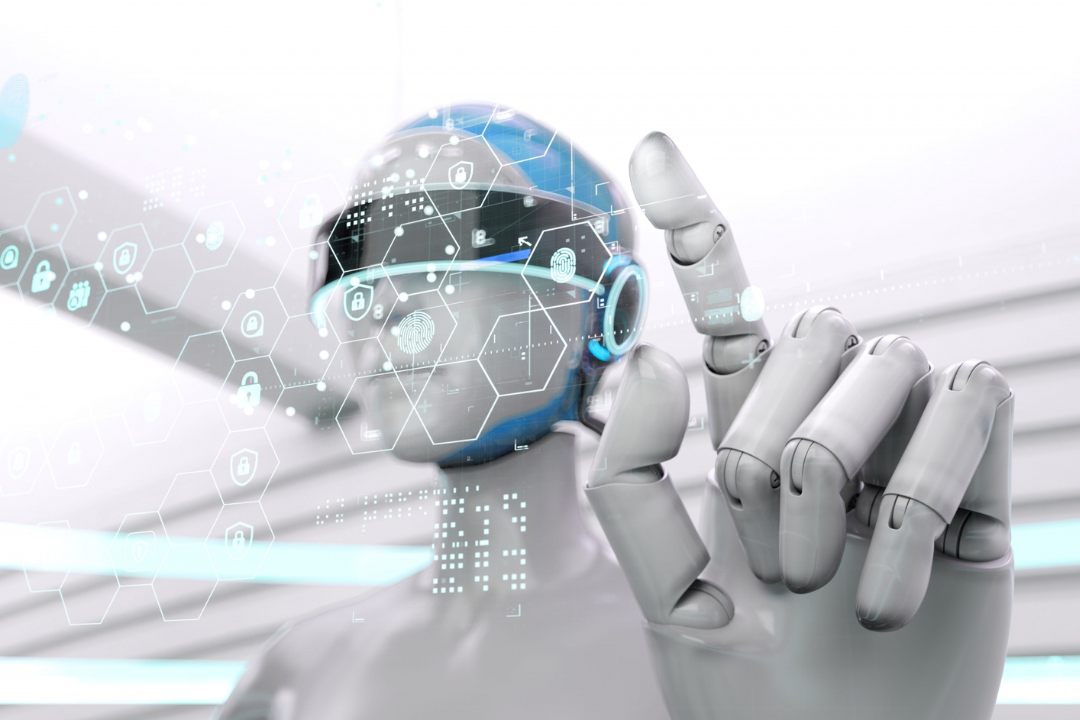 コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント
コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方
お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方 お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ
お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ