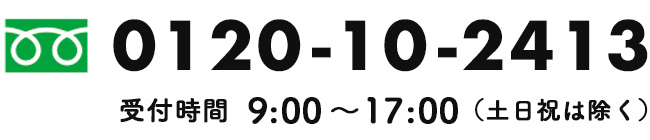訪問介護事業所の新人オリエンテーションについてお悩みではないでしょうか。
人手不足に悩む介護業界において、求人に応募してもらうだけでも一苦労。しかし、やっと採用できたスタッフに長く勤務してもらえるようにするためには、丁寧なオリエンテーションが欠かせません。
今回の記事では「訪問介護事業所でヘルパーを辞めさせないための新人オリエンテーション」と題して解説します。オリエンテーションで伝えるべき内容や、研修において大切なことについて説明しますのでぜひ参考にしてください。
1.初日オリエンテーションで伝える内容

入社初日のヘルパーさんは不安でいっぱい。早期退職を防ぐためにもオリエンテーションはとても重要です。
オリエンテーションの内容は、それぞれの事業所で決められたルールで行われています。いつスタッフが入社しても同じ内容で研修を実施し、もれなく大切なことが伝えられるように準備しておく必要があります。マニュアルや新人スタッフに渡す資料などはあらかじめ用意しておくと良いでしょう。
ここからは、初日のオリエンテーションで伝えると良い内容を解説します。
事業所について
まずは、これから働く事業所について理解を深めてもらいます。事業所のパンフレットなどがあると分かりやすいかもしれません。
説明しておくべき内容は以下の通りです。
- 事業所の基本情報
- 提供しているサービス内容
- 組織図・職員紹介
- 理念・方針
- 就業規則
- 急な欠勤の連絡方法
事業所の目指すべき姿を共有することは、新人スタッフのモチベーションアップにつながります。また、業務上のルールをあらかじめ理解しておくことで、安心して勤務が開始できます。
ヘルパーとしての心構え
介護の仕事は、ご利用者の健やかな暮らしをサポートする尊い仕事です。また、高齢者に携わる仕事は、時として命に関わる場面に遭遇することも考えられます。そのため、オリエンテーションではヘルパーとしての心構えを共有しておくことも重要です。
- 介護職の職業倫理
- 個人情報の保護
- 人権擁護・虐待防止
- 高齢者の自立支援
- 法令遵守
初めて介護の仕事に就くヘルパーはもちろん、経験者に対しても改めてしっかりと伝えておく必要があります。事業所のサービスの質を向上させていくためにも、初日のオリエンテーションを通して志を同じにすることが大切です。
接遇・マナー
介護はサービス業です。ご利用者やご家族と関わる仕事なので、接遇・マナーはしっかりと身につけておかなくてはなりません。
接遇・マナーの5原則は以下の通りです。
- 挨拶
- 身だしなみ
- 言葉遣い
- 表情
- 態度
ご利用者との信頼関係を構築するためには接遇・マナーの基本を忠実に守り、常に気持ちの良い対応を心がける必要があります。介護の現場では、ご利用者との距離が近くなりすぎて馴れ馴れしい対応になってしまうことがあります。距離感が近づくとより親しくなり、カジュアルな接し方になることもあるかもしれませんが、タメ口や赤ちゃん言葉などはNGです。
親しみを込めた接し方が喜ばれる場合もありますが、ご利用者はお客様であり、人生の先輩であることを念頭において接する必要があります。常に相手がどう捉えるかを考えてコミュニケーションを取るようにしましょう。
介護の基本知識・技術
介護の基礎知識や技術を研修します。
内容の一例は以下の通りです。
- 食事介助
- 排泄介助
- 入浴介助
- 更衣介助
- 移動・移乗
- 家事援助技術(調理・洗濯・掃除など)
- 認知症対応
- 介護保険制度について
- 訪問介護サービスについて
- 高齢者の特性・疾患
- 感染症対応
介護技術については、ご利用者のお身体やご自宅の状況により対応が異なるため、実際の現場で身につけることが多いでしょう。しかし、基本的なことだけでも事前に理解しておくと安心です。
リスクマネジメント
介護現場は、事故やクレームなどのリスクが多い職場です。事業所として事故防止のために取り組んでいることや、これまで起きた事故やクレームの事例を共有しておくと注意喚起になります。特に訪問介護サービスの場合には、事故が起きた場合の初動はヘルパーが一人で対応しなくてはなりません。事前に報連相の徹底や事故の対応方法などを理解した上で実際の勤務に入ってもらいましょう。
また、気になることがあれば些細なことでも気軽に報告してもらえる環境を作っておくことが、大事故を防止することにつながります。
記録・情報共有
訪問介護は、ケアマネジャーのケアプランをもとにサ責が作成した訪問介護計画書通りにケアを行います。記録の目的や伝わりやすい記録の書き方を説明し、情報共有の重要性を理解してもらうことが大切です。
最近では、介護ソフトを使用している事業所も増えています。スマホやタブレットの操作方法など、細かいことも事前にレクチャーしておくとスムーズです。
2.初回同行訪問で伝える内容

座学が終わったら、ご利用者の自宅への初回同行訪問です。
ご利用者宅への道順・訪問時マナー
ご利用者のご自宅への道順は、地図などを用意して説明すると場所が分かりやすいでしょう。訪問した時の自転車、バイクなど乗り物の置き場所なども伝えておかなければなりません。
訪問時のマナーが悪ければ、近隣からのクレームにつながることも考えられるため注意が必要です。
ご利用者の情報・援助内容
ご利用者の情報は、ご自宅に訪問する前に事前情報として伝えておきます。心身の状況・疾患・家族についてなど、あらかじめ頭に入れた上で訪問するとスムーズです。
介助については、手本を示しながら説明したり、実際に見守りのもと実施してもらったりしながら身につけていきます。
難しい援助でなければ1度同行訪問して、あとは一人で実施してもらうのが通常です。数回同行したら一人で訪問しなければならないため、訪問から記録まで一通りの流れを丁寧に伝える必要があります。
新人オリエンテーションで大切なこと

新人スタッフが安心して勤務をスタートさせるために、大切にすべきポイントを確認しておきましょう。
不安なままひとり立ちさせない
大抵の介護現場は人手不足でバタバタしているため、オリエンテーションに時間をかけることが難しいと悩んでいます。しかし、不安なままひとり立ちさせることは、新人ヘルパーに大きなストレスを与えてしまうため注意が必要です。慣れないまま現場に入りケアがうまくできなければ自信を失ってしまい、最悪の場合には事故やクレームにつながりかねません。
細かい注意点などを的確に伝え、できるようになるまで丁寧に指導してからひとり立ちしてもらうことが早期離職を防ぐことにつながります。
忙しい介護現場でなかなか時間が取れないのはどの職場でも共通の悩みです。しかし、そこをうまく乗り越えることが長期的な目線で考えるととても重要です。
こまめにケアを確認する
新人オリエンテーションは、同行訪問してひとり立ちすれば終わりではありません。理解できているかや困っていることはないかをこまめに確認し、相談しやすい雰囲気作りをすることが大切です。
特に訪問介護の場合は、ヘルパーがケアを行う現場をいつも近くで見られる環境ではありません。何がうまくいかないのか、何に困っているのかを常に確認できないため意識的な声掛けが必要です。
目標を設定する
モチベーションを保ちながら仕事をするためには目標設定を明確にすることも大切です。
定期的に面談を設定し、できていることやできないことをチェックし目標達成につなげます。小さな目標を積み重ねるためにチェックシートなどを活用するのも一つです。今後のスキルアップの道筋を明確にし、目指すべき将来像を思い描ければ長く仕事が続けられます。
事業所としても、特定事業所加算を算定するための要件の一つに「個別研修計画」の作成があり、目標を達成するために個々に合わせた研修の実施が求められます。一人ひとりのヘルパーに対しスキルアップの道筋を立てることは、事業所全体のサービス向上につながるでしょう。
教え方を統一する
新人オリエンテーションの内容は、指導側によってばらつきがあってはなりません。統一していなければ新人スタッフが混乱してしまいます。
オリエンテーションで伝えるべき内容はマニュアル化しておき、常に同じ内容が伝えられるようにしておきましょう。新人オリエンテーションのプログラム内容が決められていなければ内容に差が出てしまい、伝え忘れやばらつきが生じてしまいます。現場の忙しさを理由にオリエンテーションがおろそかになってしまうことも考えられます。
感覚に頼らず、誰が指導しても同じクオリティーのオリエンテーションが実施できるように準備しておくことが大切です。
ヘルパーを辞めさせない環境づくりを

今回の記事では、訪問介護事業所における新人オリエンテーションについて解説しました。
訪問介護は一定の研修を終えると現場に直行直帰の場合には顔を合わせることが少なくなります。そのため、意識的にコミュニケーションを取り情報共有を心がけることが大切です。
安定的な事業所運営のためにも、スタッフが安定的に働いてくれる環境を整えていきましょう。
介護記録はテレッサモバイルで

最近では、訪問介護でも介護ソフトを導入し、サ責とヘルパーのコミュニケーションが取りやすいように工夫している事業所も増えています。
訪問介護の介護ソフトを導入したいけれど、迷っている事業所にはテレッサモバイルがおすすめです。テレッサモバイルは、訪問介護サービス実施記録をLINEで報告できる介護記録ソフトです。幅広い年代になじみのあるLINEアプリを使用することで、スマートフォンの操作が苦手な方にも使用しやすくなっています。ヘルパーさんの記録や情報共有のハードルもぐっと下がります。介護ソフトで情報共有しやすい環境が整っていれば、安心して援助に入ることができます。サ責も、タイムリーに状況が把握しやすいためヘルパーのフォローがしやすくなるはずです。
また、テレッサモバイルを利用している事業所は、オプションでオンライン研修サービスも利用することができます。
ヘルパーの定着のため、特定事業所加算の取得・継続のためにも、定期的な研修は必須です。しかし、研修計画を立て、実際に研修を実施するというのはかなりハードルが高いという声も多く聞かれます。
テレッサモバイルを利用した情報共有、オンライン研修サービスを活用し、ヘルパーさんが辞めない事業所を作っていきましょう!
投稿者プロフィール

-
特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所での勤務経験。
介護福祉士、介護支援専門員の資格を活かし、高齢者やその家族、介護現場で働く方々のお役に立てる情報をウェブメディアなどで執筆中。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則
お知らせ2026年1月6日訪問介護の利益率を劇的に改善する経営戦略と黒字化の鉄則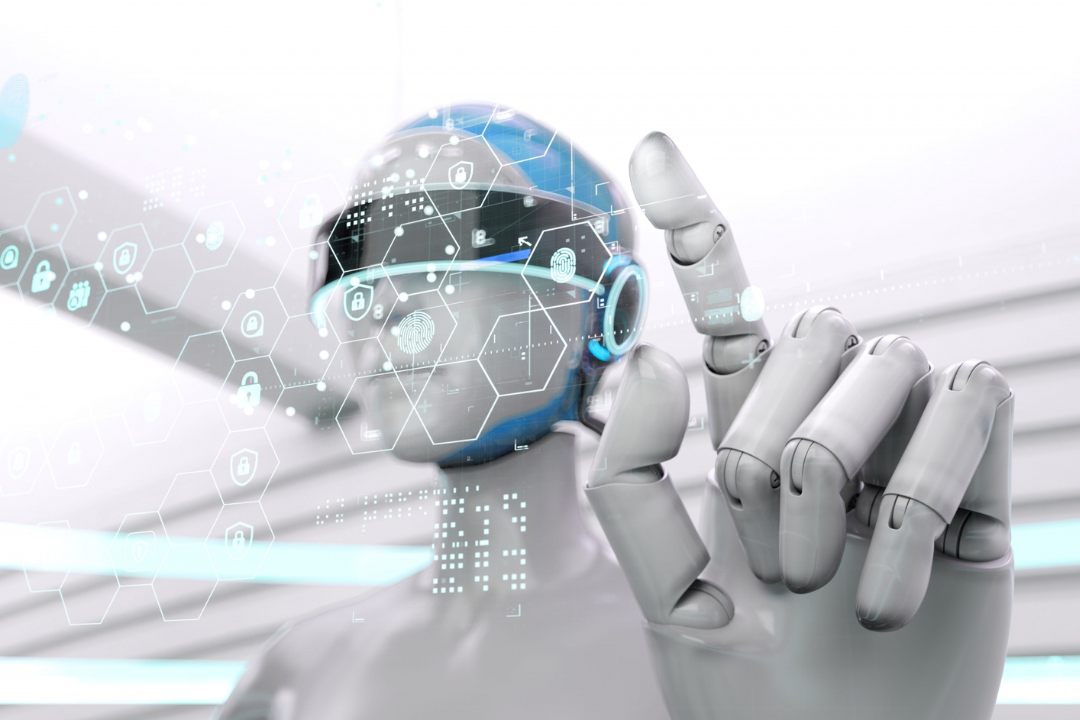 コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント
コラム2025年11月14日介護業界のAI活用|人材不足・業務負担を解決するポイント お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方
お知らせ2025年10月30日サ高住の介護記録を効率化|おすすめソフトの機能と選び方 お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ
お知らせ2025年9月13日訪問介護の現場で役立つヒヤリハット事例と防止策まとめ