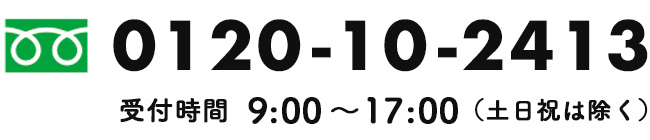訪問介護サービスを行ったら作成するのが、実施記録。
提供したサービスの内容を具体的に記録するものです。
従来の記録は紙を使用していましたが、最近では電子化が進んでいます。
この記事では、訪問介護サービスの実施記録について、手書きと電子化の違いや、電子化によって押印は必要なのか否かといった疑問に答えていきます。
訪問介護のサービス実施記録について

訪問介護サービスの記録用紙に手書きで記録する場合と電子化記録した場合の違いについて見てみましょう。
記録用紙の実施記録
一般的な手書き用の記録用紙は複写になっており、利用者名、利用時間、実施サービス内容、利用者の状態などについてそれぞれ記載します。
利用者印欄が設けられているため、利用者に押印してもらい、訪問介護実施記録の複写の1枚を控えとしてお渡しするのが一般的です。
電子化した実施記録
利用者名、利用時間、実施サービス内容、利用者の状態など記録する内容に大きな違いはありませんが、スマートフォンアプリなどから入力することが可能です。
紙の記録用紙を持ち運ぶ必要がなく、利用者印や複写での控えが基本的にはなくなります。
記録用紙と電子化した実施記録の違い

手書きの記録用紙と電子化した実施記録では、記録する内容に違いはありませんが、提出方法や管理方法が大きく異なります。
特にに実施記録を電子化することはメリットがたくさんあります。
具体的にはどんなメリットがあるのかを解説します。
記録したらすぐ送信できるから、提出忘れがない
スマートフォンアプリを使用した実施記録であれば、必要事項を入力して送信するだけで提出完了。
記録から提出までがスムーズなので、うっかり提出忘れなんてことを防げます。
直行直帰ができるから、時間を有効活用できる
事業所が遠い場合や、1日に何件も訪問する場合など、記録用紙の提出に負担を感じている人もいるでしょう。
電子化できれば、用紙を提出するためにわざわざ事業所に出向く必要がないため、時間を有効活用できます。
もちろん直行直帰も可能です。
交通費の節約にもなりますよ。
記録用紙の保管スペースや管理の手間の削減ができる
紙の記録用紙の場合、ファイリングをしたり保管したりするスペースが必要ですが、電子化できれば、管理スペースの節約ができたり書類管理の手間が省けたりするでしょう。
紙の記録は自治体によって差がありますが、最低でも3年、多いところで5年の保管義務があります。
それだけの期間紙を保管するだけでも大変なことです。
利用者印欄がないので、印鑑を押す必要がない
紙の記録用紙には利用者印欄があり、利用者にサービス終了後、押印をお願いするのが一般的です。
電子化すれば利用者印欄がなくなるので、利用者に印鑑を押してもらう手間がありません。
実施記録は印鑑不要でも問題ない!?

従来の紙の実施記録には利用者印欄があったため、印鑑を押してもらうことが当たり前でした。
では、電子化によって押印のない実施記録は書類として不備とならないのでしょうか。
近年、介護保険やケアプラン、サービス提供記録などの介護に関する書類で、押印の原則廃止の方針が出ていることを知っているでしょうか。
実施記録について、「指定居宅サービス等の運営基準 第十九条 2項 」には以下の記載があります。
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
指定居宅サービス等の運営基準 第十九条 2項
このように、サービスの記録について、「実施記録への押印をしなければならない」と書かれている部分はありません。
実施記録はサービス内容が適切であったかを証明するために、必ず必要な書類です。
記入内容に不備があると、適正なサービスかどうかを証明できないため、場合によっては介護報酬の返還を求められる可能性もあるでしょう。
しかし、事業者が行うべきことは、記録を残すことと利用者から記載内容について申し出があった場合に提示することです。
押印は必要ありません。
しかし、利用者印欄があるのに押印がなければ、実施指導などでその部分が目につきやすくなってしまいます。
担当ヘルパーが押印をもらうのを忘れた場合、再度利用者宅へ出向くこともあるでしょう。
押印が必須でなければ、押印忘れがないかのチェック業務に時間を取られることもありませんね。
脱ハンコ!電子化するならテレッサが安心

押印の必要をなくし、実施記録を電子化するには、「テレッサmobile」がおすすめです。
LINEを使用して実施記録を作成できるアプリで、自分のスマホからお友達登録をすることで利用できます。
使い方はとても簡単で、必要事項を入力して報告ボタンを押せば提出が完了。
事業所では送信された実施記録をリアルタイムで閲覧できるため、利用者の状況把握や報告内容のチェックが素早く行えます。
利用者の押印は必要なく、利用者控えが必要な場合は、紙の介護記録と同じフォーマットで出力してお渡しすることも可能です。
また、「テレッサmobile」の魅力のひとつに、1年間の記録用紙のプレゼントがあります。
スマートフォンやLINEなどITツールに慣れていないヘルパーさんが多い場合は、手書きの記録用紙と併用しながら慣れてもらうことができますよ。
まとめ

実施記録に押印は必須でないことがわかりましたね。
電子化することで、押印の必要がないのはもちろん、実施記録の作成や管理がより簡単に行えるようになるでしょう。
スマホアプリ「テレッサmobile」であれば、手書きの記録用紙と併用しながら徐々に慣れていくことができます。
電子化を進めたいと思っている事業所の方は、ぜひ導入を検討してみませんか。
Author Profile
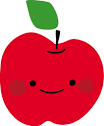
-
5年にわたり祖母の介護を経験。その経験を元に、介護の世界へ。
現在はライターとして介護の記事を中心に執筆中。
Latest entries
 お知らせ2023年12月5日LINEスタンプ、はじめました
お知らせ2023年12月5日LINEスタンプ、はじめました コラム2023年11月27日【導入事例】テレッサmobileを導入して得られたメリットとは?株式会社ライフケア・ビジョン様
コラム2023年11月27日【導入事例】テレッサmobileを導入して得られたメリットとは?株式会社ライフケア・ビジョン様 コラム2023年5月16日サービス実施記録を紙から電子化するメリットと方法
コラム2023年5月16日サービス実施記録を紙から電子化するメリットと方法 コラム2023年5月16日介護システム|テレッサモバイルは、介護タクシーには使えますか?
コラム2023年5月16日介護システム|テレッサモバイルは、介護タクシーには使えますか?